
こんばんは。今日もお疲れ様でした。
先日、当サイトのライターさんと415系の話をしていました。「交直流版211系」として登場するはずだったあの車は、結局運用を分けることが面倒くさい、と言う理由でMT-54モーターを積んだ415系になってしまいましたね。別形式として名前を付けられるのならどのような名前だったのだろう。
さて、この415系1500番台、実は211系と共通するところが多々ありまして。34編成しかいないマイナーな彼ら。注目されることなく消えて行ってしまった編成も多かったのではないでしょうか。
今回は、ネットにも資料としてあまり乗っていない「415系1500番台」を、211系オタク目線で解説!残り僅かな活躍となってしまう”彼ら”にスポットを当ててみましょう。
時代に追いついた新車

1980年、「赤電」と呼ばれていた常磐線・北九州地区の電車。当時は各地域3つの形式が活躍。常磐線の電車には「401系・403系・415系」という③形式が、北九州地区では「403系・423系・415系」活躍していました。この3形式の特徴はこんな感じ。
- MT-46モーターを搭載した「直流・交流50Hz対応車」:401系
- MT-46モーターを搭載した「直流・交流60Hz対応車」:421系
- MT-54モーターを搭載した「直流・交流50Hz対応車」:403系
- MT-54モーターを搭載した「直流・交流60Hz対応車」:423系
- MT-54モーターを搭載した「直流・交流50/60Hz対応車」:415系
457系統よりは簡単ですが、それでも難しいですね笑
この3形式が混ざって運用を行っていた常磐線・北九州地区。車内はオールボックスという、通勤お断りな設備でした。
1985年、中距離電車では異例の「オールロングシート車両」が登場します。この年、常磐線沿線である茨城県つくば市において、「EXPO’85 国際科学技術博覧会」、いわゆる「万博」が開催されました。この万博に関する輸送力増強を目的として製造され、イメージチェンジということで塗装が白色ベースに青帯の「白電」と呼ばれるタイプで落成しました。既存の車両も順次変更されたようです。今の常磐線主力車両「E531系」の青帯の基となった塗装ですね。

さて、このころ北九州地区では「421系」をはじめとした最初期車の劣化が目立っていました。そこで、車両を更新することにします。では、その車両はどのようにして手配する予定だったのでしょうか。当時の計画は何と「常磐線に新車を投入して、415系500番台を北九州に玉突き転属させる」というもの。このころ、関東圏では205系や211系と言ったオールステンレス車が新車として登場していました。同時に、401系の老朽化が目立ち始めていたため、常磐線にも投入することが決定。万博で増産された415系500番台だけでは足りなかったようです。そこで、イメージチェンジをはかる目的でオールステンレス車体の新車が登場します。
この「新車」こそ、415系1500番台だったのです。
ちなみに、415系1500番台で置き換えられた「白電の415系500番台」が北九州に転属したため、北九州の車も白電塗装に改められたようです。本州と違い若干青帯が明るかったとか。
当初は新形式のつもり

当初、別形式として設計されていた415系1500番台。ですが、「運用を行う際に差があると面倒くさい」と言う理由から、同一形式に纏められてしまいます。1500番台の由来は「オールロングシートである500番台のマイナーチェンジ車だから」という説が一般的なようです。
415系1500番台は同時期に出た直流中距離電車、「211系」の影響を強く受けた車。車体は211系ベース、台車は211系電車とほぼ同等のものを使用するなど、随所に211系要素を取り入れた設計となりました。
あくまで「415系の増備車」と言うところがポイント。
あくまで415系の増備車であるため、制御装置等は従来の車と同じ「MT-54モーター」を搭載、前面行先表示器は細形(従来車と幕を共用するためという説が濃厚)、ジャンパ管を設置するなど、しっかりと「415系」としての側面も兼ね備えます。
当初の計画では、全編成が勝田電車区に配属され、北九州の415系はすべて玉突き転属で補う予定でした。しかし、民営化を直前に控えた国鉄が「経営が軟弱になるであろう九州地方に新車を投入しよう」という計画に変えたため、小倉電車区にも新製配置されることになります。これが、今の「Fo1509編成~Fo1521編成」です。
その後、JR東日本も製造を続け、415系1500番台は4両編成34本と、1電動車ユニット、3両の特殊車両からなる合計「141両」が製造されました。
旧性能にはあらがえず

そんな415系1500番台でしたが、JR東日本車は登場からわずか20年前後で廃車の道をたどることになります。2007年には常磐線にグリーン車が登場。同時期に、つくばエクスプレス対抗として130キロ運転が開始されます。これにより、常磐線の中距離電車はE531系に統一。以後は友部以北や水戸線などで細々と活躍していましたが、やはり115系や415系初期車と同じ、「MT-54」という旧世代モーターを搭載した415系1500番台は使いにくかったようで、早々にE531系に置き換えられてしまいました。
既に209系やE231系などで省エネが行われていたところに、東日本大震災が重なったのが原因だったのかも?
わずか20年ちょっとの「新車」。あまり注目されることもなく、2016年に東日本からは消えてしまいました。一方の九州では…?
まだまだ現役!!

JR九州では、関門トンネルを介して「本州」と「九州」を結ぶ命綱のような路線、「JR九州 山陽本線・鹿児島本線」に415系1500番台が使用されています。「ステンレス車体・交直流電車」と言う点が、塩害を多く受ける海峡トンネルにおいて使いやすかったようです。関門トンネルは交直流切り替えを必須としますもんね。
そんな415系1500番台もついに置き換わるのではないか、という噂が囁かれています。交直流版211系電車も、もうすぐ終わりなのかもしれませんね。
実は6次車まで存在!

さて、34本しかいない415系1500番台ですが、実は「6つのグループに分けることができる」んです。このグループ分けは、同時期に製造されていた211系電車の影響や、時代に合わせてマイナーチェンジしていった結果。なんか意外と沼ですねこの形式。
と言うわけで、今回も見ていきましょう!全6グループの紹介です。
なお、ここからは特筆すべき車両以外、「下二桁」のみを記載します。車番「1512」だった場合は、「12」とだけ表記します。
あくまで415系なので、鋼製車含めモハユニット単位で交換されることがよくありました。
①国鉄1次車(01~08/サハ-1701)
よく見たら403系と連結している…?
常磐線勝田電車区向けに製造された1次車8本と1両。
- 運転台後ろの窓が小さい
- 網棚が網目状
- 方向幕横にビートが無い
- ライトケースは国鉄タイプ
など、同時期に製造されていた211系電車の「国鉄2次車」の特徴を受け継いでいます。
常磐線向けに登場したため、常磐無線アンテナを取り付ける準備工事を施工したうえで登場。結局使われることはなかったようです。
また、従来の415系では使用されていなかった方向幕は準備工事状態で登場。代わりにサボ受けが設置されました。なお、方向幕の準備工事は鋼製車と違い「方向幕を白幕で固定したうえ、点灯させない方式」だったのが特徴。埋め込まれてはいなかったようです。
基本的に鋼製車と同じ設備を持ったため、車内スピーカーは箱型のものが別で用意されていました。
このほかに、1両だけ「サハ411-1701」というセミクロス付随車が登場します。既存の編成に存在した「中間封じ込めクハ」を置き換え、クハを「先頭車」として動かせるようにすることにより、編成数を増やすことを目的として製造されました。
1501編成を除き、全車解体済みです。
ちなみに一部編成は211系のごとく日焼けをしていたようです。あの顔にはつきものなんですかね?
1501編成

1501編成以外は…。と書いたところで察しの良い方はお気づきでしょう。1501編成は現在JR九州に譲渡され、「Fo1501編成」として活躍しています。
E501系の甲種輸送の際、ばったり顔を合わせた415系は彼だったようです。久しぶりの再会、一部界隈で盛り上がっていましたね。
②国鉄2次車(09~21)

九州向けに増備されたグループ。国鉄1次車と同じく方向幕は準備工事状態で登場しましたが、常磐無線アンテナが無いのが特徴。当たり前っちゃ当たり前ですけどね笑
このグループから、
- 貫通扉が3枚とも拡大
- 方向幕横ビートが追加
- ライトケースはJRタイプ
という211系国鉄5次車の流れを汲んでいます。211系国鉄5次車と言うと、名古屋地区向けに配属されたあの0番台2本が該当しますね。
また、415系オリジナルとして、「従来は鋼製車と同じく箱型で設置されていた車内スピーカーを、パンタグラフ下を除き211系と同じく空気取り入れ口内に設置した」という特徴があります。以降の増備車もこの方針で増備されます。

なお、13本製造されたうちの「1511編成・1512編成・1513編成」は日本車両が製造したため、ライトケースは日本車両初期車特有の「国鉄と同等のライトケース」が採用されています。また、1512編成は若干日焼けしているのが特徴的。
鋼製車よりも明るい青帯をまとって、全編成が現在も運用中です。
③JR1次車(22/23)
国鉄が解体され、民営化された1987年。415系1500番台の製造が再開します。ここからは全てJR東日本が製造した車両になるため、211系のような会社ごとの差は無いようです。
同時期に製造されていた211系電車のJR東日本1次車と同じく、
- 網棚はパイプ状に変更
- 列車無線アンテナを搭載したため、常磐無線アンテナ準備工事は省略
といった変更が行われています。なお、方向幕は未だに準備状態です。鋼製車がなかなか改造されなかったのが原因ですかね笑
④JR2・3次車(24~27/28~31)
さて、時代は平成に入った1989年。未だに415系1500番台は増備されていました。しかし、このJR2次車、前代未聞の415系だったんです。
国鉄民営化が行われ、各地域ごとに「JR」が運営を行うことになった日本の鉄道。全国レベルでの大転属劇は消えました。そこで、JR2次車は「JR東日本には不要な60Hz対応機器を取り外した、交流50Hzにしか対応しない415系1500番台」というタイプで登場することになります。実質403系1500番台ですね。
JR西日本の415系800番台(113系からの改造車)ですら50Hz対応をしていたのに…。
ほかにも、「車内の床下点検蓋を省略」が行われていたりします。211系よりちょっと先取りしてますね。また、1528編成よりも後の車は屋根上ベンチレーターをステンレス製に変更していました。
ちなみに、このグループも方向幕は準備工事状態で登場していたようです。
そんなJR2次車最終増備車のK534編成。東日本大震災により、原ノ町駅から長らく動けずにいました。
あの日、667M列車として終点 原ノ町駅に14:45に到着したこの編成。1分後に地震が襲い、そこから全く動けなくなった彼。原ノ町駅より南側の線路は流され、彼は帰る手段を失いました。
震災から5年後の2016年。陸送により郡山総合車両センターに運ばれ、ひっそりと彼は車生を閉じたのでした。
⑤JR4次車(32~34+α)
クハ415-1901との編成を解消してからも単独で運用を行っていました。
ついにあの化け物が登場。5次車です。方向幕はやっと搭載された状態で落成しました。サボ受けが新製当初から搭載されていないのが特徴的です。
5次車は3編成が製造。そのほかにオールロングシートの「モハ-1535」ユニット、オールロングシートの「サハ-1601」、そして「クハ415-1901」が製造されました。この「サハ-1601」は、クハ411-16**が入る場所に連結されることからこのような番台分けになった、と言われています。
この「バケモノ」のようなクハ415-1901、常磐線の混雑を緩和する目的で試験的に投入されました。編成は都度都度変わることがあったようですが、基本的に「1500番台4連+サハ-1601+モハユニット+クハ415-1901」という組成だったようです。
なお、結果的にこの形式は2ドアだったことで混雑を助長する存在になってしまい、朝夕の一部列車のみ入るという本末転倒な運命をたどります。結果的にこの1両だけだったのですが、設計は後の215系や、中央線快速電車・青梅線のグリーン車にも受け継がれています。
受け継がれたライトケース
719系カタY-10編成。この編成のクモハ(719-5010)は他の719系と違い、国鉄型ライトケースを付けているのが特徴的です。しかし、このライトケースは当初から取り付けられていたものではありませんでした。
2009年4月2日。山形県南陽市 奥羽本線の高畠駅~赤湯駅間において、自動車との踏切事故が発生します。これにより、Y-10編成のクモハの前面が大破。先日起きた幕張209系の事故のような状態になってしまいました。
そこで、このY-10編成を直すのに使われたのが当時解体されていた415系、と言われています。そのため、415系国鉄車由来のライトケースが使われた、と言われていますが、真相はいかに。
情報源がないものの、多くの人がこの通説を唱えているため、事実なんだろうなあと思います。2010年の雑誌「とれいん」に顔面だけがない415系なるものが乗っていたそうです。それなんですかねえ。
後にも先にも、国鉄ライトケースを持った719系はこの車両だけでした。
まとめ
さて、今回はちょっと路線を外れ、415系1500番台を見てみました。交直流版211系の位置づけである彼ら。車体は新しいのに、床下の機器のせいで悲惨な運命を辿ることになったもの、そんなの関係ない!と今でも働いているもの。配属された場所によって命運が分かれる、そんな車でした。
更新を受けた九州の彼らは、今日もMT-54の爆音を鳴らしながら走る。一方、「時代に流された東の車」は消え去る。
九州地方での活躍もあとわずか。実は僕、415系1500番台を生で見たことがないので、生きているうちに僕も九州に行きたいですね笑
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
ちなみにこの記事熱で寝れなかったときに書いたので文がいつもよりおかしいかもしれません笑
Special Thanks
画像提供ありがとうございました。
小森江さん
ふぺちゃん
ホームドア
- 晩年眠いので記事の信憑性はないかも(適当)



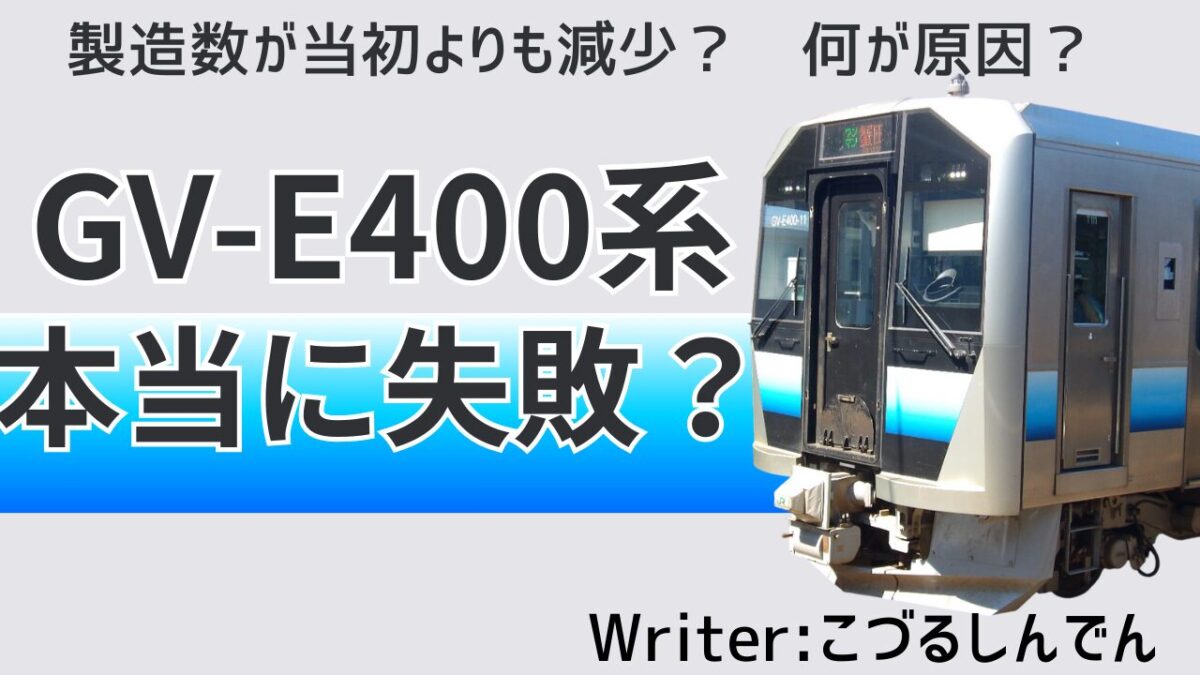


コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。