
こんばんは。今日も1日お疲れさまでした。秋も中盤、大阪万博ももう終了。結局行かなかっちゃったな。
先日、電車が好きな友人と遊んでいたところ、「211系の続編記事はまだか。」と催促されてしまいました。なんか読んでもらってありがたい反面、最近電車をしなくなった自分に少しダメージが。ありがたいんだけどね、うん…。
というわけで、久しぶりに211の長野車の続編です。今回はボックス3連の「1000番代」について取り上げてみましょう!
追記:KATOで車内だけを変えたら編成が作れないのか、と言われました。床下・ライトケースが違って幕横にビードがあるんで超絶加工めんどいです…。
※当記事では「固定クロス」を「ボックス」と呼称し、「転換クロス」を「クロス」と呼称します。予めご了承ください。
ボックスとロング

その前に、国鉄とJR東日本では「中距離列車用車両」に対する考え方が少し違っていたことを皆さんはご存じでしょうか?
この差は、211系と415系・E501系などの国鉄末期~JR黎明期に登場した車に大きく表れています。その後も113系、115系などの車にも順次JRの考え方が普及することになります。
移動することに質を出した国鉄

「中距離電車」、いわゆる「中電」は、各駅停車に対して遠くまで移動する、という考えだった国鉄。客車で誕生したボックスシートを電車に設置したのが始まりです。
80系、111/113系、115系、401/403/421/423/415系…。基本的にドア付近以外は全てボックスシートが採用されてきました。これらの車両は「新宿 – 甲府」「上野 – 黒磯」「上野 – 平(いわき)」と言った、長距離運用に投入される車両でした。

なお、例外として、115系1000番代と115系3000番代(異例の2ドア車)については、車端部がロングシートになっているのが特徴的。1000番代は雪切室設置の影響、後者はドア数の関係と思われます。なお、どちらもトイレがある先頭車はトイレ前にボックスシートが採用され、1000番代は雪切室が設置されていない全ての付随車がトイレの有無にかかわらずボックスシートが採用されました。トイレから出てきたときに目が合って気まずくならないための配慮席と言われている、あれです。
1982年、国鉄に異例の「オールロングシートの中距離列車車両」が登場。常磐線向けの「415系500番代」です。
常磐線は上野 – 取手間において「殺人電車」の異名があるレベルでの混雑率を誇り、当時最長12両編成で乗り入れていた中距離列車では捌くことができませんでした。そこで、混雑緩和を目的に、オールロングシートで登場することになります。結果的に先代の401系初期車の置き換えを行うことにもつながりました。

1985年、茨城県において当時世界最大規模の博覧会、つくば万博(EXPO’85)が開催されることになりました。そこで、1984年から1985年にかけて常磐線の車両を8両編成・12両編成から15両編成に増結することになり、先に登場した500番代に増結中間車が組まれることになります。
この時に登場した増結中間車こそ、車端部ロング、ドア間ボックスの「700番代」という車両。増結用車両のため、中間車のみが製造されました。この「車端部ロング、ドア間ボックス」という形態こそ、現在の地方路線の車両の基本となるものです。
同時期、東海道線・東北高崎線の使用車両である、113系・115系初期車が老朽化しており、新型車両を登場させることで置き換えを行うことが計画されます。その新型車両こそ、211系電車だったのです。
211系は南関東向けの車が「基本編成8両ボックス+2両グリーン」「付属編成5両ロング」、北関東向けの車が「5両ロング×2」「5両ボックス×1」という布陣で登場。2:1の比率で登場したため、南関東向けの車とは立場が逆になっています。グリーン車が組み込まれたのは民営化後のことでした。
ロングシートの車は、翌年登場した211系顔の415系1500番代(サハ411-1701除く)と同様にトイレ前のみボックスの片側のみが設置されました。それ以外は皆さんが知るような、ロングシートです。
とにかく捌くしかないJR東日本

一方、JR東日本はどうでしょうか。中距離列車車両の位置づけである、「近郊型」のうち、都心部を走る車は「E217系」「E231系近郊タイプ」、「E233系3000番代」「E531系」の4車のみ。しかし、これら4形式はボックスシートを積んでおり、この車両の中で「オールロングシート」の車は存在しません。どうしてこんなにボックスシートを積んでいる車が少ないのでしょうか。そして、オールロングシートにしないのでしょうか。
その謎を知るには、1987年の3月までさかのぼることになります。
国鉄最末期から問題になっていた「都心の混雑問題」。1987年3月24日に長野総合車両センターN29編成が「試験車両」としてオールロングに改造されたのがきっかけでした。そこから1年。1988年3月に民営化後初の211系、シマA23(今のナノN312)編成、シマA24(今のナノN313)編成が落成しました。同時にボックス車も登場すると思われましたが、ボックス車は登場しませんでした。ここで、「全車完全なボックス車」というのは東北向けの車を除き消滅することになります。
ちなみに、ナノN29編成はだいぶ不評だったようで、2002年12月10日のリニューアル工事をもって車内が元のボックスシートに戻されました。
翌年19989年には113系・115系の初期車のボックスをトイレ前を除きロングシートに改造。もともと後期車とのシートピッチ感覚が違うことで車内サービスにも差が出ており、サービス改善とともに輸送力増強を目的として改造されました。大体20%ほど多く乗ることができるようです。
113系1500/2000番代・115系1000番代以降の車はシートピッチが急行型並みとなっていたため、問題にはならなかったようです。
この改造は所属する場所によって異なっており、「小山115系」は基本編成の7両編成、「田町(後に国府津)113系」は基本編成11両のうち、グリーン車以外の9両、「大船(鎌倉)113系」はグリーン車前後の2両のみが改造されました。

同時期に登場した南関東向け211系もロングシートとなり、ボックス車は国鉄製造の田町×基本編成6本、小山×5両編成11本、神領×4両編成2本の少数グループになりました。
その後登場した「新性能電車」「E電」の中距離列車車両では、E501がオールロングシートで登場しましたが、トイレが設置されてないこともあり不評を買い、その後のE231系近郊タイプからは一部の号車にのみボックス車を連結するという方法に出ます。
しかしこれでも混雑は捌けないようで、結果的に最新型の「横須賀・総武快速線系統E235系」はオールロングシートの「通勤型」として登場することになりました。
全11編成を一挙に紹介!

というわけで、11本すべてが現役の1000番代を一挙ご紹介!今回も次車ごとにご紹介します。
①国鉄1次車(N317/N318/N319編成)

列車無線アンテナ準備工事で登場した国鉄1次車。大きなアンテナ台座が特徴的です。N317/N318/N319編成の3編成が該当。
N317編成は3000番代トップナンバーであるN306編成と同時に、N318編成とN319編成が後日同時に落成しました。
N317編成に関してはクハ(長野方先頭車)のJRマークが少しずれているのが特徴的、N318・N319編成はクハが少し日焼けしているのが特徴的です。N318のクモハも見方によっては少し左にずれているのかな?
この3編成、前々回ご紹介した原型モケットを搭載した編成なんです。最近ヘタってきたけどまだまだ現役で活躍してほしいですね笑
全編成、延命は施工されていません。
②国鉄2次車(N320/N321/N322/N323/N324編成)

N320編成からN324編成の5編成が該当する国鉄2次車。列車無線アンテナが登場当初から搭載されている編成です。
このグループは何と言っても日焼け。N320編成だけが原型モケットを積んでいます。
N320/N321は両先頭車ともが日焼けしており、N322編成もクモハ(高尾方先頭車)のみが日焼けしています。N321は塗装がガサガサなことも相まって、もはや末期的な車になっています笑

また、N323編成のクハとN324編成は前面JRマークが若干左に寄っているのが特徴。全編成が特徴を持つ2次車、個性派が揃っていますね!
N320編成・N322編成・N323編成は延命済です。
白幕(N322)

さて、一時期長野管内・中央本線・中央線のTLを賑わした「白幕」。N322編成の長野方先頭車に取り付けられ、話題になりました。
1回目の白幕
2025年4月17日に長野に入庫したこの編成でしたが、長野側LEDに不具合があったようで交換をしないといけませんでした。しかし、LEDの在庫が手元になく、仕方なく保存していた高崎車の白幕を取り付けて対応することにしました。と言うのが通説のようですが、本当なのかどうなのか。
一時期東海道線の幕なのでは?という予測も飛び交いましたが、長野総合車両センター内での幕回しの際、「両毛線」「高崎線」などといった高崎A36編成と同等の幕が見られたことから、高崎車の白幕と判明しました。
N322編成は過去に編成札の盗難にも遭っており、長野側先頭車の編成札が大きいのが特徴的。延命化も相まってN314/N315とは違った、別の白幕が誕生しました。

同年8月21日の出庫の際にはLEDに戻っていたため、約4カ月間の姿になりました。久しぶりの白幕は懐かしさと違和感の塊でしたね笑
ちなみに、諏訪湖花火大会の際などに「白幕」と言って英字表記の「白い幕」を投稿する方が毎回いらっしゃいますが、長野の白幕はこの「英字表記がない白い幕」(国鉄時代から使っていたやつ)を指すため、若干ニュアンスが異なってしまうようです。
2回目の白幕

さて、そんなこんなでLEDに戻って運用を行っていたN322編成。しかし、10月23日に再度故障してしまいます。今回はすでに長野県内で故障の旨が伝わっていたようです。
結果、10月27日より再度「白幕」に戻したうえで運用に復帰することに。田町・幕張・N314/N315編成に積まれている「青幕」ではなく、今回も「白幕」だったのが特徴的。これは、「快速」の収録順が高崎タイプと幕張田町タイプで異なるためなのでしょうか、はたまた、単に予備がないだけなのでしょうか。真相は謎に包まれています。
ドアステッカー(N323)

また、N323編成の高尾方先頭車の海側真ん中のドアには「長野のドア注意ステッカー」が貼り付けられています。先代115系に取り付けられていたタイプのものであり、現在ではしなの鉄道115系・飯山線キハ110と211系N323編成でしか見ることができません。
中央本線の車と言えばこのステッカーの印象が強いので、N323編成のステッカーを初めて生で見た時は懐かしさと嬉しさがありました。
③国鉄3次車(N325編成)

1000番代の中で一番ノーマル編成である国鉄3次車のN325編成。1編成しか該当しない3次車が一番ノーマルってなんか変な感じですね笑
日焼けもしていない、編成札も普通、そんなN325編成ですが、運転台すぐ後ろの窓が真ん中だけ拡大されています。これが唯一の特徴でしょうか。
④国鉄4次車(N326/N327編成)

2編成だけが該当する4次車。N326・N327編成が該当します。
N326編成は長野で1,2を争うレベルで日焼けしているのが特徴。N327編成はクモハ側が日焼けしているのが特徴的な編成です。N327編成は延命工事が行われているようです。
ステンドグラスラッピング(N326)
N326編成と言えばステンドグラスラッピングでしょうか?

2023年の12月に行われた甲府 – 大月間録音電車に使用されたN326編成。モハ(真ん中の車両)の窓にはこのようにステンドグラス風のラッピングが行われていました。
半年ほどの短期間でしたが、この編成に当たったらステンドグラスがあるという特別感がありました。

なお、実際の録音電車は日中に行われました。甲府以東で3両編成が日中に走るのは現在では定期で無いため、違和感がすごかったです。
今話題の「E131系200番代」

さて、この前ついに一部が表に出たE131系。うっすら感じではいましたが、いよいよかといった感じです。
今回の投入は豊田なのか長野なのか何もわかっていませんが、とりあえず中央本線向けなのか確定のようですね。廃車電車(長野211系のあだ名)が本当に廃車電車になったらつまらなすぎる。
いよいよ新時代が幕開けする中央本線。中央本線への普通列車新製車投入は115系1000番代投入時の1977年を最後に行われていなかったため、およそ50年ぶりの完全新車となりそうです。いよいよかあ…。
執筆時点で判明している情報(労働組合が提示した資料)は
- 3両編成が20本の60両
- オールロングシート
- トイレ付き
- パンタグラフは一つ
- 運用範囲は立川 – 松本 – 篠ノ井 – 長野。富士急行線は未定。
- 2026年度頭に車両投入
- ワンマンは2027年春から。27年時点では211系と併存。
- E131系の区分は「200」。
の8つ。
どこに配置されるかも決まっていないのであまり深くは言及できませんが、211系が都内で見れるのも、あと少しなのかもしれませんね。最後の神奈川県の国鉄車はもしかしたら南武支線の205系…?
仙石線と同じような投入方法になりそうですが、公式のプレスリリースが出るまで待ちましょう。
211系のボックス車は高尾に来るいわゆる「豊田運用」という運用に優先的に入るという動きがあります。さて、E131系の導入で運用がどう変わるんでしょうか。
豊田運用

211系3両編成の中に存在する一つの運用グループ、「豊田運用」。長野を出て大糸線と篠ノ井線を走った後甲府に来て、そのまましばらく高尾あたりを走り、最後に長野県内で快速運用をして長野に帰ると言う運用形態が取られています。
この豊田運用、ボックス車が優先的に充当されるという法則があります。
長野県内の3両編成はロングシートだった!なんて経験をしたことがある人も多いかと思いますが、あれは「長野県内は一部運用を除きロングシートが優先的に充当される」と言う法則があるからなんです。
富士急行線にも乗り入れる豊田運用。今後どうなっていくのか、注目したいところですね。
まとめ

今回は211系の1000番代について、ボックスとロングを巡る時代の考え方の違い、個性豊かな彼らの特徴、E131系が今どんな車と言うことが判明しているかについて、ほんの少しだけ見てみました。山梨県は豊田運用の範囲に入るため、3連は1000番台の方がなじみ深いです笑
最初期編成はいよいよ40年を迎える今年度。彼らにとって大きな転換を迎えるのも、もう遠くない話なのかもしれません。
今回の記事はここまで。最後までご覧いただき、ありがとうございました!
撮影に来る際は、ぜひ「マナーとルールを守って楽しい撮影」を!
- 晩年眠いので記事の信憑性はないかも(適当)
- 2026年2月14日JR東日本E233系はあの路線に配備予定だった?【頓挫した車両計画】(首都圏JR普通電車編)
- 2026年2月8日JR東海213系5000番台、最後のJR東海非VVVF車の歴史を辿る!
- 2026年2月2日東武鉄道鬼は外!👹福は内!🫘秩父鉄道で「豆まき電車」が運行!電車で福を呼び込もう!
- 2026年1月19日JR東日本“横浜線”はなぜ全部”横浜駅”に行かない?~横浜線の歴史を紐解く~


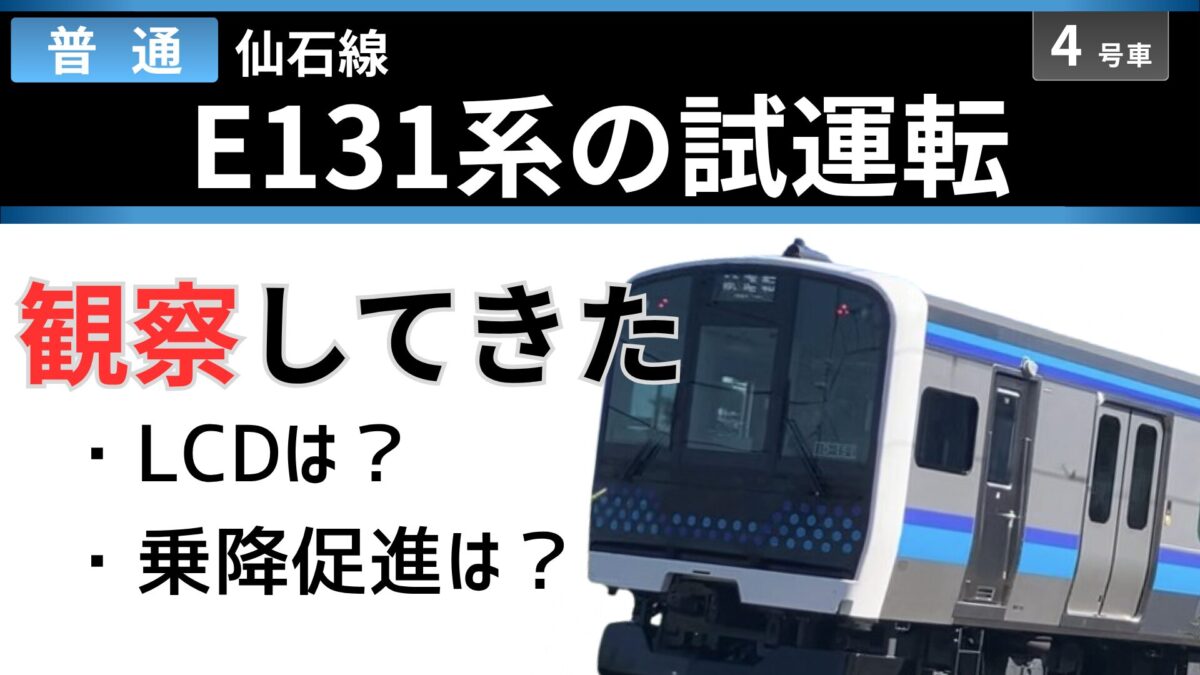
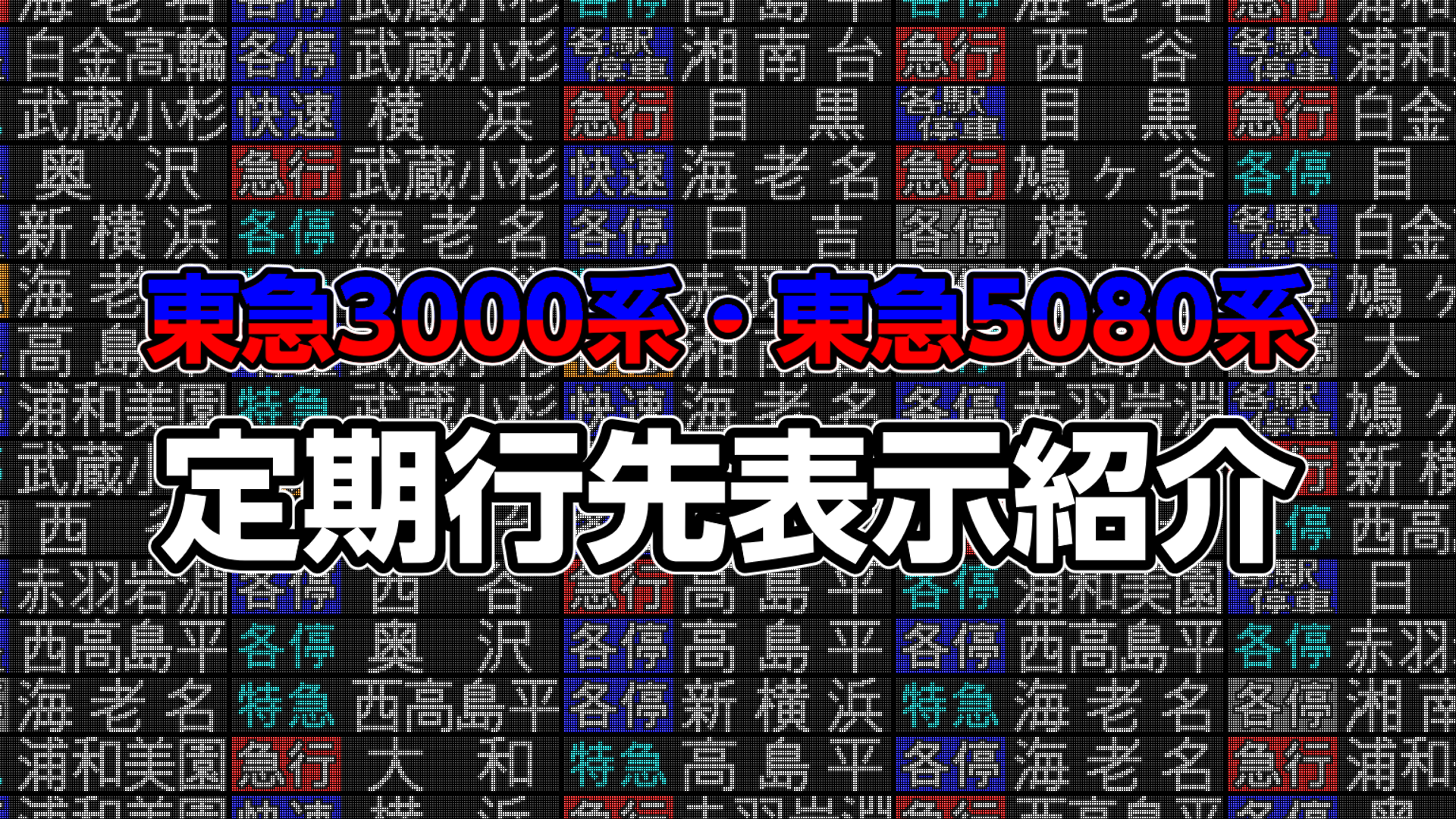

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。