
まずはお疲れさまでした、381系
2024年6月15日、本日をもって定期運行を終了した列車があります

381系国鉄特急型電車
日本ではついに最後となった国鉄形車両を使用した特急電車で、1967年の581系より伝統を継ぐ電気釜スタイルの前面を兼ね備えた最後の電車として、多くのファンに愛されてきた電車でした。日本各地で見られたこのスタイルが見られるのも、6月15日の特急やくも1号が最後となり、そのやくも1号も定刻であればこの記事が上がったタイミングで終着駅の出雲市についているはずです。
私自身、岡山県に母方の実家があるということでよく381系は駅や留置線で眺めており、黄色い電車と並んで止まっているのを見かけると「帰ってきたなぁ」と実感していたものでした。
さてそんな381系ですが、よく言われるのが「げろしお」や「ぐったりはくも」などの蔑称。381系に搭載されている自然振り子制御は、カーブに入った際の遠心力で傾くタイプの振り子なのですが、この場合タイムラグが生じやすく、振り遅れや揺り戻しなどといった、曲線に入ってから傾き、直線になってもなかなかまっすぐに戻らないなどの現象が多発していました。これらが原因で乗客は平衡感覚を失い、他形式と比べて酔いやすいことから、このような蔑称が付けられるようになってしまいました
が、そんな381系が日本の、いや世界の鉄道に残した功績は計り知れないレベルで存在します。
今回は、そんな381系の引退に哀悼を示しながら、381系の残した多くの功績について語っていこうと思います。
世界初!車体傾斜装置を採用した営業用車両

これは言わずもがな、と言ったところでしょう。
日本に限らず、世界では山がちな路線や曲線の連続する路線というのが、数多く存在していました
そこで多くの国で、車体傾斜装置を使用してこれらの路線を速達化する計画があり、そのための試験用車両が各国でこぞって開発・研究されてきました
日本の場合は、1969年に登場した試験車591系が381系の開発を後押しした…というのは有名なお話しですが、世界に目を向けてみれば、イギリスのAPTことClass370形や、イタリアのペンドリーノの量産先行車ETR401系などなど。
各国で研究が盛んにおこなわれていたのですが、毎日運転の定期列車として世界で初めて運転を開始したのが1973年7月10日、日本の中央西線でのこと。
油圧を利用した強制振り子で苦戦する他国をよそに、日本は日本らしく自然の力に任せた車体傾斜装置「自然振り子式」を採用することで、保守の簡略化と速達化を同時に成し遂げるという快挙を達成しました。遠心力万歳。まぁこれが後年になって問題になったりしたんですけどね…(笑)
これまで485系などの特急電車の場合は、「本則(カーブの半径に則り決められた制限速度)+5km/h」が限界だった速度向上が、381系では「本則+20km/h」と大幅な速度向上を成し遂げることに成功しました。要するに半径600メートルのカーブの本則が75km/hなところを、485系は80km/hで通過可能な一方、381系の場合は95km/h、カントの高低差を最大値の105ミリメートルに設定した場合は、通常車両が105km/hで侵入可能なところに125km/hで突っ込めます(ただ381系の設計最高速度は120km/h)。ちなみに485系は110km/h。たかが15km/h、されど15km/h。極端な話600メートルのカーブが続くような路線を1時間連続で走った場合は同じ特急型でも15kmもの差ができます。東海道線で例えるなら東京~蒲田間に匹敵ます。
その効果が大幅に表れていた路線として有名なのが、阪和・紀勢本線の特急「くろしお」。この列車は、1985年から1年半ほど381系と485系が併用されて運転されていた時期があったのですが、天王寺~新宮間を485系使用のくろしお号の場合は4時間30分程度で結んでいたのに対して、381系の場合は3時間30分程度と、1時間以上の差があったのです。もちろん停車駅に差はあれど、結局この問題でクレームが入ったらしく、特急やくもからの転用で玉突きする羽目になったのです
万能特急485系でも、カーブだけは克服できなかったか…
世界初の車体傾斜を採用した営業用車両である381系。その後の車体傾斜に関する技術の発展はすさまじく、現在ではヨーロッパやアメリカをはじめとした世界各国で、車体傾斜装置を採用した列車が多く活躍しています。こうした面で見ると、鉄道の歴史を大きく変えた車両だったと思います。
余談:という名の小噺

余談ですが、当初591系の量産車は東北本線の特急「はつかり」や「やまびこ」などのために試験をしていたのはご存じでしょうか。さらに、最高時速130km/hの運転も計画されており、当時の国鉄としてはかなり先進的かつ意欲的な技術だったことがうかがえます。当初の目標は表定時速100km/hを超える列車を設定すること。現在ではサンダーバード号がこの記録を超えて運転していますし、JR民営化後なんかは多くの列車がこの表定速度を超えていますが、当時の国鉄にとっては、高速バスや飛行機の発達する状況において喫緊の課題だったのです。
結局、東北新幹線の早期着工の決定により、費用対効果が薄まることから591系の量産化計画は一旦白紙撤回し再検討をすることに。そんな中で注目されたのが、すでに成熟していた車体傾斜の技術。この技術だけをフィードバックして、直流専用車として量産したのが381系なのです。
その後、130km/h運転の電車は、1989年に登場した651系に端を発し、現在では特急列車はおろか、一部の快速電車まで130km/hでの運転が実施されています。
こうした成果を生み出すきっかけを与えてくれた591系という車両こそ、現在でも日本が「鉄道大国」として走り続けられている大きな理由の一つにあると思います。そういった面では、381系だけでなく591系という車両にも多くの感謝してもしきれませんね。少なくとも空転滑走再粘着装置などの装置は、591系の試験結果を踏まえて出てきたと言っても過言ではないでしょう。
というわけで、まずはこの「車体傾斜による高速化」のお話でした。
日本初のアルミニウム合金を使用した特急電車!

意外と知られていないのですが、日本初のアルミ合金を採用した特急電車ということ。
現在でこそ、アルミ合金を使用した特急型電車は、多くの鉄道会社で走っている上、新幹線なんかも今ではアルミ合金を使用していますが、その走りは381系だったのです。
アルミ合金を採用した理由としては、お察しの通り軽量化と低重心化が目的です
車体傾斜を採用する車両としては、車体が振り子で動き回る分、重心を下げることで安定性が上がります。
そこで、車体部分は重量を軽くして、下の方の機器に重心が固まるようにということで鋼鉄に比べて軽量なアルミ合金を使用して軽量化して、高速走行中の安定性を高めたのです。
当時、アルミの製造技術は発展途上で、東京メトロ6000系や国鉄301系などが出てきたばかりのころ。これらの車両は造形が単純なため、加工の難しかったアルミ車体でも採用できましたが、381系のような湾曲した前面や車体傾斜のために裾を絞った車体などなど、当時の技術ではかなり難しい製造技法だったと思います
この頃から、現在新幹線の製造の際にも使われている叩いたり機械で整えたりして車体にはめる「プレス技法」という技を確立していくことになりました
現在日本で活躍する多くのJR特急はアルミ合金製で、日立ではA-trainとしてその技術を海外、特にイギリスのClass800などにも広げていますが、こうした現在の特急列車の姿を、381系が多くかかわっていたのだと思うと感慨深いですね
クーラーを床下に埋め込んだ日本初の電車

元来鉄道車両の冷房装置は、屋根の上に乗せてそこから客室内へ送るのが主流でしたが、1958年に登場した20系寝台客車からは解放感を出すために床下にスペースを設け、そこから空調をダクトで送る手法が採用され、屋根上がスッキリした美しいスタイルになりました
一方、電車は走行用の機器を床下に積んでいることが多かったり、保守的な観点で屋根上に設置したほうが交換などが楽なため、床上に設置する場合が多かったですが、現在では新幹線をはじめとしたさまざまな特急列車は床下に冷房装置を付けて重心を低くするような工夫が見られます
で、この床下冷房を電車で初めて採用したのがこの381系。車体傾斜採用による低重心化を図るため、屋根上に搭載している機器を床下に設置することに。結果的に床下はギチギチなので、いくつもの余裕を生み出したうえでクーラーを配置。配管を通して車内へ空気を送るシステムを採用しました
Wikipediaなんかで調べてもらえるとわかるのですが、381系は床下に機器を大量に積んでいるせいで、交直流電車の485系より床下がギッチギチです。隙間がないです。
そのため、走行に必要なユニットは通常2両1セットなところを、クハ(サロ)+モハ+モハ(クモハ)のT-M-M’の3両1セットに変更するなどして、国鉄時代のごちゃごちゃした床下の中でもなんとか運用できるようになりました。改めてよくこれで交直流電車作ろうとしたよな…
現在ではVVVF制御装置を採用したことや機器の小型化が進んだことで、低重心の特急をとしてJR東日本の特急列車で多く採用されていますが、それを実現させたのは紛れもなく381系でした。
また、新幹線の空気抵抗の削減策として300系からも床下クーラーになっていますので、これが新幹線の高速化の立役者になったということは言うまでもないでしょう。
日本最速(公式記録上)の狭軌在来線車両

381系は1985年11月25日に湖西線で実施した速度向上試験において、近江中庄駅付近で179.5km/hという狭軌鉄道世界最速をマークしました(JR東日本のTRY-Zが超えてるみたいな噂はありますが…)。この記録は、40年近く経った2024年現在でも破られていません。
この試験にはモハ4両に両端クハを組み込んだ日根野電車区所属の6両編成2ユニットで試験に供していました(まぁ試験後半にユニット無視した6M2Tの8両で試験に供していた姿が確認されているらしいですが)。
まぁおそらくこの走行試験の目的は徹底した低重心化を図った381系の実力を確かめるためのものであり、また381系の自然振り子に油圧を利用した補助を行う制御付き自然振り子の研究のためにも走行をしていました。
その結果が低重心での走行結果は、日本最速の特急「はくたか」や「サンダーバード」として活躍する681系電車に引き継がれ、制御付き自然振り子はJR四国の2000系気動車を発端に日本を代表する列車として運行がされていました。
ちなみに、試験に供された6両はその後通常のくろしお運用に戻り、2011年の287系投入まで活躍していました。
最後の国鉄形特急電車

そして何より、最後の国鉄時代から引き継がれた伝統の顔立ちをした最後の特急電車ということ
先述したように、1967年デビューの583系より引き継がれた電気釜スタイルと呼ばれる丸っとした先頭形状をした国鉄スタイルの特急型車両として最後の活躍をしている電車こそ、この381系なのです
関東圏では185系の定期運用が消滅した2021年以降は、最後の国鉄形を使用した特急電車として多くのファンに親しまれてきたこの車両
1981年度予算で作られた伯備線向けの381系は、いよいよ気付けば42年もの長い期間、伯備線の「顔」として、そして何より伯備線の電化の「象徴」として、長い間多くの方たちを運び続けてきました
いよいよ今日、その「顔」にも世代交代が訪れました。
出雲地区に住む方をはじめ、山陰地方の多くの方の協力の下で得られた伯備線の電化開業。今はそれさえも「当たり前」の景色に変わっています。

しかし、以前伯備線を利用した際に降り立った「美袋駅」の駅舎の屋根に、架線柱用に切り欠いた跡があったことから、改めてこの歴史の生き証人が、置き換えを前に私たちに何か問いかけているようにも感じました
多くの方の努力があってこそ、381系は伯備線で走ることができ、令和の時代まで走り続けた
携わった皆様には、感謝してもしきれませんね…
終わりに

語りたいことはまだまだありますが、これぐらいがちょうどいいと判断して、今回は終わりにしたいと思います
485系や185系などの陰に隠れがちな車両でしたが、その残した功績は、日本はもちろん海を越えた先でもその歴史的価値はかなり高い車両となっています。
世界の陸路を縮めた車体傾斜式の車両の功績をツラツラとお話ししました。
ちなみに、皆さまとの国鉄形特急の思いではありますでしょうか。ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。
改めまして、1972年より52年にわたる活躍をしてきた国鉄特急381系。本当にお疲れさまでした。
余談:ゴハチさんからのお知らせ
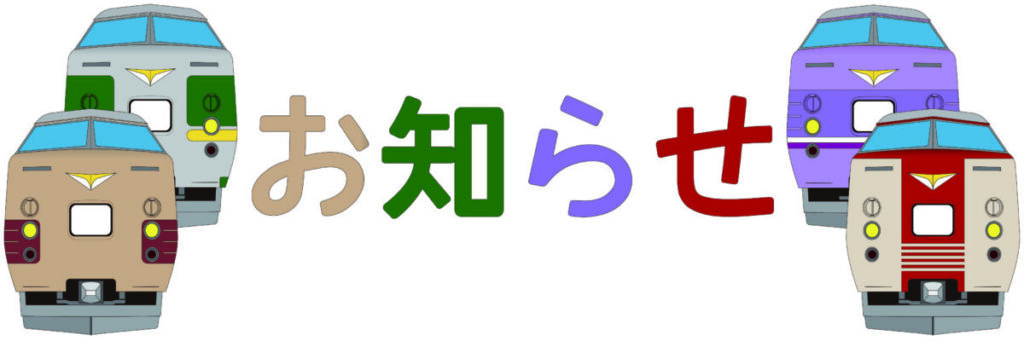
ここからは余談なのですが、わたくしゴハチさん、この記事をもってブログ活動をしばらく休止します
理由として、学校課題に追われながら動画を制作したりブログを書いたりしているため、今年の目標だった「3DCAD作品を生み出す」という目標から遠のいているような感じがしたためです
ブログの編集はやめないですが、しばらく休止期間として、3D作品の制作に専念させていただきます
休止中もTwitterの方では毎日何かしらつぶやいているので、フォローしていただけますと幸いです
活動休止期間として、8月半ばごろまでを計画していますが、場合によっては9月ごろまでずれ込む可能性もあります(まぁ今月末くらいに気分転換に書いた記事でも出そうかな…)。
あと、活動休止中はマシュマロで質問募集もやってるので、匿名でなんでも質問してみてください(多分返答まで時間かかりますが…)
というわけですので、よろしくお願いします。

-
別名:停車駅馬鹿
コメントは遠慮なくどうぞ。返信するかは気まぐれです。
- 2026年1月24日まとめ・考察【速報】藤沢駅 新駅舎開業! 橋上改札で藤沢地域の移動はどう変わる?
- 2026年1月17日記事小田急線藤沢駅旧改札が使いにくい!
- 2025年12月12日JR西日本227系 ついに山陰進出へ!【2026年ダイヤ改正のお知らせ】
- 2025年12月3日記事E233系 トタT71編成を撮りに行く


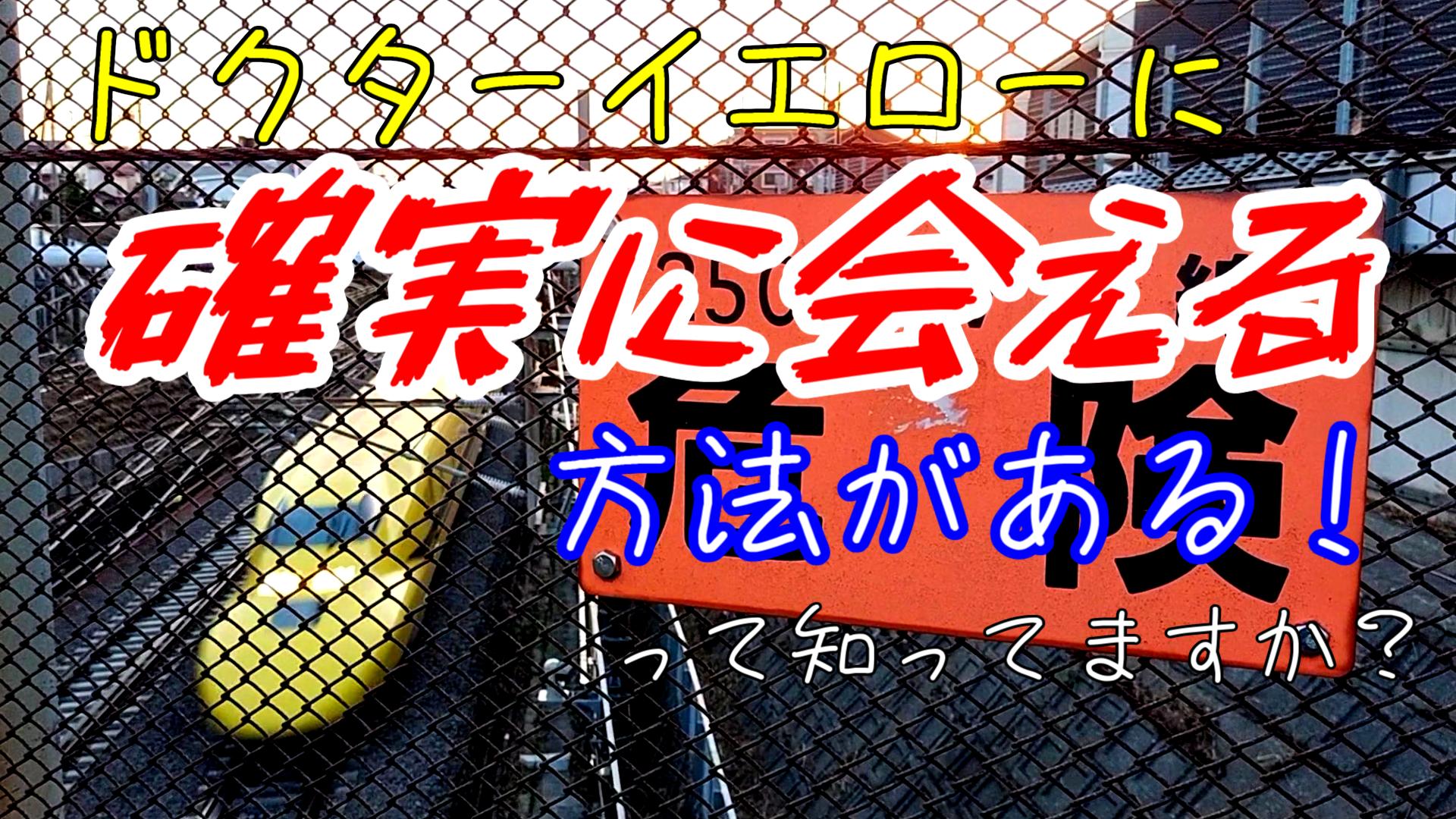
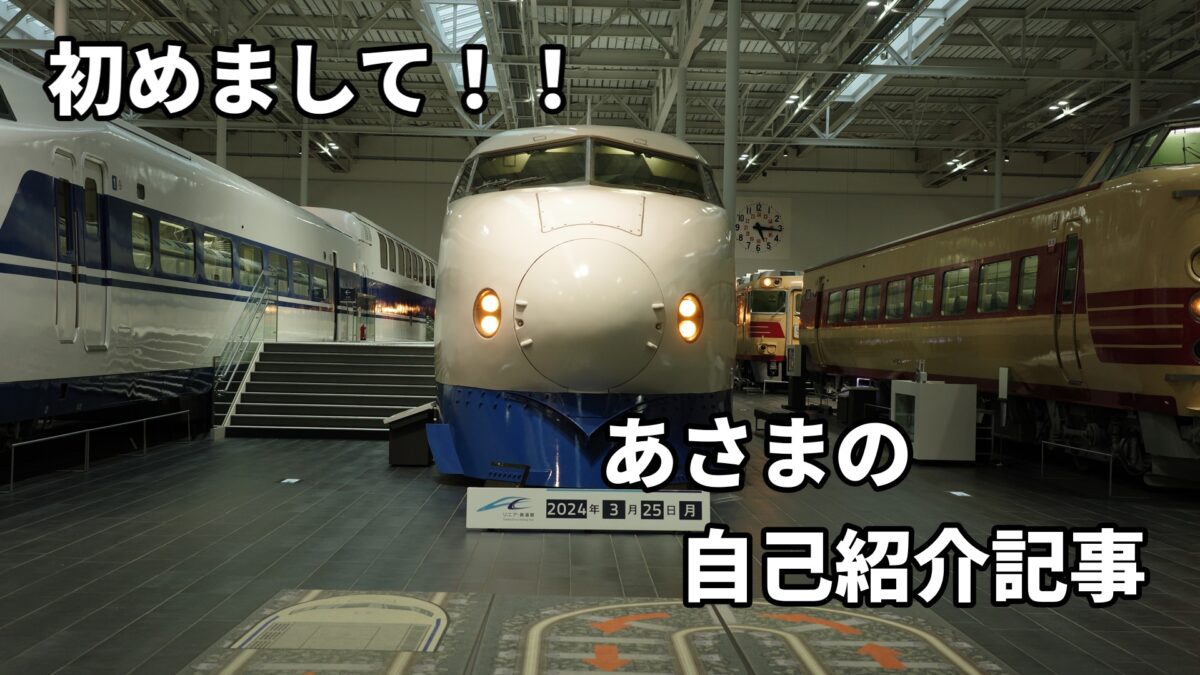

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。