
ご無沙汰してます。最近鼻炎に非常に悩まされているふぺです。

福岡県北九州市にある門司港駅を起点とし、九州一のターミナル博多駅や「火の国」こと熊本県の中心地熊本駅を通りながら九州の南部にある鹿児島駅を結ぶ九州の代表路線こと鹿児島本線。そんな鹿児島本線には2つすごく似た駅名が存在しているのを知っていますか?それが「福間駅」と「赤間駅」です。福間駅と赤間駅は非常に近く、どちらの駅もそこそこの規模を持ち普通、快速列車も全て停まるうえに特急も何本か停まります。そんな福間駅と赤間駅ですが似てるようで実は結構大きな違いがあるのです。今回はそれをゆるく見ていこうと思います。
駅紹介 〜福間駅〜

最初に紹介するのは福間駅。博多駅でもよく見かける駅名ですね。
福間駅は単式ホームが1面1線、島式ホームが2面4線の計3面5線ある地上駅で普通列車、快速列車、特急列車(一部通過)の全ての種別が停まる主要駅であります。日中の博多方面からから来た普通列車は半分以上が当駅で折り返し、小倉方面へ向かう区間快速もほとんどが当駅から各駅に停車します。そんな福間駅が快速停車駅となったのは1972年のダイヤ改正から。なおその8年後のダイヤ改正にて鹿児島本線の特別快速が廃止された影響により快速停車駅から除外されましたがすぐに快速停車駅に復帰しました。また福間駅に停車する特急列車も年々増えてきており、
特急ソニック1、2、3、4、6、44、45、46、47、48、49、51、53、55、56、57、58、59、60、201、202号、特急きらめき1、2、3、4、5、6、8、10、12、14、101号、特急リレーかもめ9、66号、特急かささぎ101号、特急にちりんシーガイア5号
の合計36本が停車しています。
ちなみにこの福間駅の所在地は福岡県福津市。なぜ福間市ではなく福津市なのかについてですがこれは福津市が最近できたばかりの新しい市町村で、旧福間町と津屋崎町が平成17年(2005年)に合併された影響でできた市町村だからです。「福津」の名前の由来は幸”福”と人が集まる”津”を合わせたのが由来とされています。
そんな福間駅の駅名の由来は開業時の地名。福間駅が開業したのは1890年、現在は福津市中央三丁目となっていますが当時の地名は宗像郡下西郷村字福間浦でした。また福間は「福満」とも読まれ貴族などの荘園が多く設置されていたようです。そして地名の由来ですがはっきりとは分かっていませんが縁起の良い「福」と船着場や漁港を表す「間」を合わせて「福間」と名付けられたと言われています。
駅紹介 〜赤間駅〜

次に紹介するのは赤間駅。ちょうど博多と小倉のほぼ中間に位置する駅になります。
島式ホーム2面4線の地上駅で福間駅と同じく普通列車、快速列車、特急列車(一部)が停車する主要駅となっています。赤間駅は1961年の鹿児島本線の門司港駅から久留米駅が電化されると団地の造成などが進み、福岡、北九州のベッドタウンとして栄え1980年には快速が停車するようになりました。
福間駅からは東福間、東郷と3駅ほど進んだ場所にありますが本数は福間駅が8時台の博多方面に特急3本、快速2本、区快1本、普通4本の合計10本あるのに対し赤間駅は8時台の博多方面に特急2本、快速1本、区快1本、普通3本の合計7本と3本ほど差があります。(小倉方面も同様の7本)
福間駅に比べると博多方面へのアクセスが若干悪いように感じますが特急の停車本数はこちらの赤間駅の方が多く、
特急ソニック1、2、3、4、7、8、11、12、15、16、19、20、23、24、27、28、31、32、35、36、39、40、43、44、45、46、47、48、49、51、52、53、55、56、57、58、59、60、201、202号、特急きらめき1、2、3、4、5、6、8、10、12、14、101号、特急リレーかもめ9、66号、特急かささぎ101、201号、特急にちりんシーガイア5、14号
の合計54本が停まります。
そして赤間駅の所属する市区町村ですが福間駅と同じ感じで赤津市…なんてことはなく福岡県宗像市となっています。
赤間駅の名前の由来は福間駅と同じく開業時の地名で、かつては宗像郡赤間村という地名でした。「赤間」の地名の由来ですが、かつて赤間は赤馬と書かれ、神武天皇東征の際に吉留の八所宮の神が赤馬に乗って現れ、里民に従軍を命じたことにちなんで赤馬と名付けたと言い伝えがあります。
福間駅と赤間駅の違いとは?
さて、では本題の福間駅と赤間駅の違いについて、福間駅が属する福津市と赤間駅が属する宗像市の特色を含めて解説していきたいと思います。

福津市はイオンモール福津のオープンやや区画整理によってベッドタウンとしての需要が増加しているほか、宮地嶽神社や玄界灘など観光スポットも充実しており、福間駅は博多駅から11駅とかなり近いうえに快速列車に乗れば20ほどで着くことができるのでベッドタウンしてはかなり優秀な場所と思われます。

対する宗像市は福岡市と北九州市の両都市の中間に位置し北除く3方向を山に囲まれている他に近年住宅団地や大学、大型商業施設が多く進出してくるなどして福津市と同様にベッドタウン化が進んでいます。また宗像大社や総合公園、玄界灘など自然を味わいながら生活することができるなどかなり注目されており、赤間駅は博多駅まで快速列車で30分、小倉駅まで40分で行くことができるのでこちらも交通の便はとても優秀だと思われます。
快速も特急も停まるうえに駅周辺には神社や玄界灘、そしてベッドタウンとしてどちらも福岡市との繋がりが強い…ここまで見ていると両駅ほぼ同じに見えてきますが「両駅共に同じ特徴を持っている」で終わらせてはあまり面白くありません。決定的に違う福間駅と赤間駅の違いを探っていきましょう。
福間駅と赤間駅、結局何が違う?
福間駅と赤間駅の決定的な違い、それは駅の役割です。

福間駅と赤間駅はどちらとも福岡都市圏へのアクセスが強いですが、福間駅は宮地嶽神社や福間海岸、波津海水浴場など住宅地のほかに観光地が非常に多く、通勤客のほかにこれらへの観光目的で福間駅を利用する人も多いです。

それに対し赤間駅は宗像大社以外に目立つ観光地がないものの、ビバモール赤間やくりえいと宗像など商業関係の建物が非常に多いほか、東海大学附属福岡高等学校や宗像市役所など宗像市の商業・教育の中心地としての役割が強いように見えます。
要は福間駅は福岡市のベッドタウンと福津市の観光地最寄駅、赤間駅は宗像市の商業、教育の中心地の駅としての面を持っているのです。
まとめ
いかがだったでしょうか?福間駅と赤間駅の両駅は先述の結論の通り決定的な違いがあるとはいえ、それ以外の部分は似てる部分が多々あり執筆していてとても面白く感じました。皆さんも家の近くの路線で似たような駅名があればどこが似ていて、何が違うのかについて探っていくのも楽しいと思います。
前回に比べるとかなり短くなりましたが以上で終わりとさせていただきます。ここまで読んでいただきありがとうございました。

- icon @Bashamichi_mm04
- 2025年12月26日その他【福岡市を横断】地下鉄空港線を自転車で走破してみた!!!
- 2025年12月14日JR九州【航空祭2025】年に1度だけ築城駅に臨時停車する特急ソニックに乗ってきた話
- 2025年12月13日記事JR九州 2026年ダイヤ改正の概要をまとめる
- 2025年12月4日JR九州【山々を越えてゆく】1日3往復!?熊本と大分を結ぶ特急「九州横断特急」で行く豊肥本線完乗旅



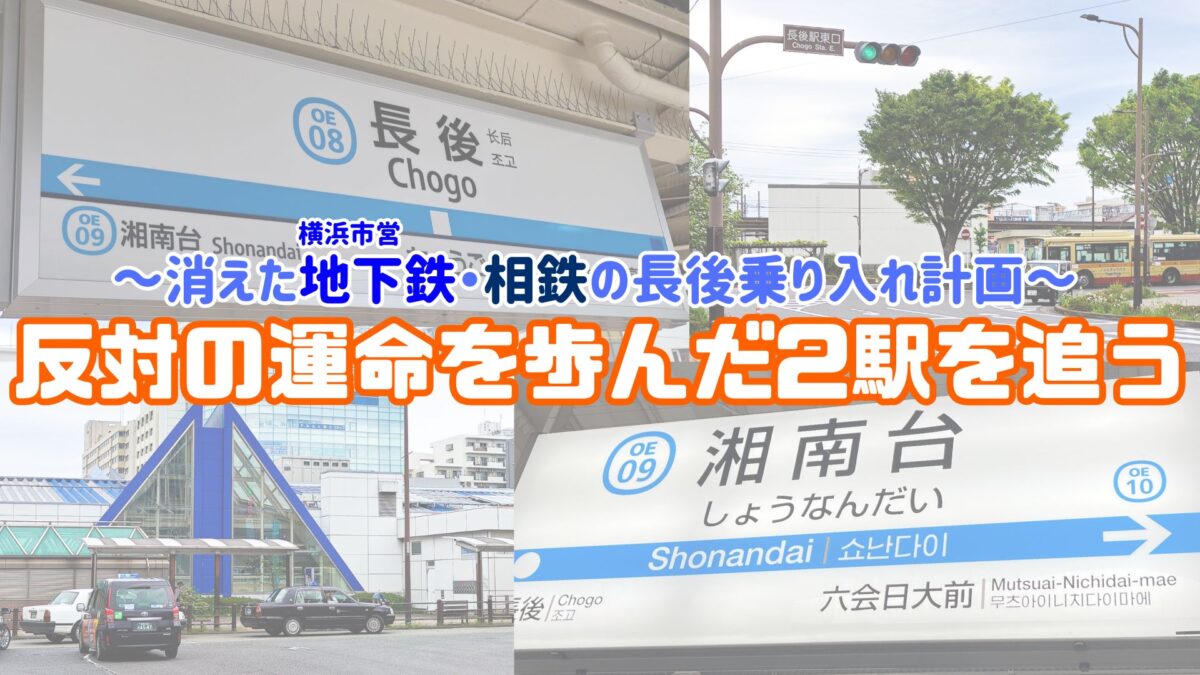

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。