
こんにちは、もりやです。
ついに夏という夏が始まろうとしてますね。やっぱり今年もコミケ…でしょうか。今回はふりとれも参加!という事でなんかいろいろと参加者の皆さんがバタバタしてますね。まぁ自分もそのうちの一人なんですけど。
そんなことは一旦置いといて東武鉄道にまたこんなニュースが発表されました。
https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/news/202506181452208ZgAhC6pt8A4HlAXktDGkQ.pdf
-2025年7月・8月臨時特急列車【スカイツリートレイン】運転について
これで座席指定特急の運用は去年の冬から3季目の会津方面特急に抜擢されました。
という訳でなぜあれほどのニートレインと化していた634型が3季目の連続抜擢を受けたのでしょうか。その理由をいくつかの視点から考えてみましょう。
それでは今日もよろしくお願いします。
634型スカイツリートレインとは

画像が前回記事と同じなのは許してください…
634型は東武鉄道が運用している4両編成の特急型電車です。具体的には2+2両編成となっているが2両編成としての運転は基本的に行われていません。もともとこれは6050型の改造工事を受けた編成となっているため、どうしても4両の組成を作る方法がこれしかないためと考えられます。
この車両は主に2017年ごろまで土曜休日で定期運用、平日では車庫で寝てる事になっており場合によっては団体電車として運転を行います。
2017年以降は臨時列車をメインに運行をしており立ち位置的には近鉄の20000系「楽」と同じような感じです。
車内は3列シートを設置しており、日光を先頭にしたとき偶数号車が進行方向左側を窓に向かって設置されているのが特徴です。また、それぞれの1号車と2号車は座席のシート配列を1-2、2-1と反対にしてることも面白い特徴になっています。
車内のモケットは編成別に第一編成が青、第二編成が赤のような色になっております。
ほかにも外装としてはこの工事で車体に合わせて傾斜させた天井まで伸びる窓が座席部分に設置してあり眺望も抜群です。
ただ、欠点としてはやっぱり改造元が窓が可変式で、さらに某日光のNE’Xと同じくらい座席と一致してないためそれこそ横方向ではアタリとハズレがはっきりと分かれるという事があります。とてもおもしろいですよね。縦はいいけど横はめっぽうダメっていう。さらに窓が固定されていないため高速走行するとガタガタと唸るため、ぶっちゃけゆっくり休んで寝るなんてことはできません。
そんな状況のコイツ、どこで変わった?
本格的に開放的な旅客運転が再開されたのは2023年。野岩鉄道線内の臨時の増発運転分から始まりました。そう、ここから再び盛り上がってまいりました。
2024年と2025年の年末年始には東武鉄道の臨時の本線系統優等種別としては6年ぶりの運用になりました。種別はスカイツリートレインとしての運転にとどまっていましたが運用は会津田島から浅草までのリバティ会津と同様の区間。なんなら停車駅に対しては東武ワールドスクウェアを通過するという点を踏まえるとかなりの好待遇となった種別です。
当時の運用についてはこちらをご覧ください。↓
そのまま軌道に乗っていき2025年の春には墨田川と権現堂のお花見する人たちへの特急として浅草と南栗橋の間を走る近距離ライナーが運転されました。そしてGWはまた冬と同じ会津田島を往復する運行されました。
そしてこの夏も土曜休日をメインにGWと同じダイヤを使って運転される事が発表されています。
団体メインの車両なのになぜ?
これには様々な要因が考えられます。その中でも特に考えられる事象を3点から解説していきます。
1.500系リバティが足りない
リバティは東武鉄道の中でも汎用として製造された車両で運用の制約が少ないという利点があります。

運用も幅広く、特急運用に対する制約が少ないのが特徴
その少ない制約故に通常の6両編成で乗り入れると輸送力の過剰となる地域や、逆に多方面への増解結ができることを活かして路線需要がひっ迫する時間帯や区間を2列車同時に併結して運転するという方法が可能です。
そのために特に繁忙期では多くの臨時列車に抜擢されることがあることがありますが、もともと運用が多すぎるあまり、臨時に出せる運用が少ないという事がおきています。
「じゃあ3次車の作成をすればいいじゃない」という事になるのですがそれこそその通りなのですが、中期の指標にはそのことが書かれていないという点からおそらく今後の量産はないものと考えられます。それに今期の余剰金62億円相当を株主に配給することも考えると、より近いうちのリバティの増備は考えられないと言えるでしょう。
まぁぶっちゃけこのリバティ会津とほぼ同じ区間を運転するスカイツリートレインがピンチヒッターとして運転される7割くらいがこのリバティが不足しているという問題にあたるわけですのでこれ以上話すことはない、と言われたらそれはそうだとなってしまいますが、じゃあなぜそのような事態が発生してしまったのでしょうか。それを次の事象で考えてみましょう。
6両固定の編成の本数が少ない
もともと運用上での制約がないために運用が多い、というか多すぎるリバティですがその裏で様々な車両が廃車されました。
有名なところで言えば250型りょうもうが出てきますね。これはもう完全にリバティ号での置き換えで廃車になりました。とはいってもこれには深いわけが…というようなものがあるのです。まぁ簡単に言えばスペーシアXによってリバティとスペーシアを置き換えそのスペーシアで一部のリバティを置き換えてその置き換えたリバティでりょうもうを置き換えるというかの有名なスペーシアデビュー時のあの大転属を彷彿とさせるようなものです。
とりあえずこのことは置いといて、この本数が少なるとどうなるのでしょうか。
まず、第一に挙げられるのは着席人数の減少です。そもそもリバティの座席の数が1編成161人、6両で322人です。この数値はスペーシアやスペーシアXの日光方面の特急の座席数より多いものの主な置き換え対象になっていたりょうもうでは398人とその収容できる人数が限られてきます。日光方面では増発というような運用をとられてたのに対してりょうもうではどちらかというと半分増発半分置き換えみたいなイメージです。これは臨時を出すほどの大増発をしている日光線では3日前に全席満席、となるため座席を確保するという事が大変になります。これで何回普通電車で帰った事か…
第二に挙げられるのは運用の置き換えができないという事です。やっぱり運用的には自由度の高いリバティを日光線に回してりょうもう号では200型で一時的に置き換えることでリバティを臨時に回すことができる、というものです。特に日光特急では臨時は特に限られた線路容量にどれだけの種別を通せるかが問題になります。とはいえ保守的な考え方をする東武、という点もあってそのようなことは今現在起きていませんが、今後起きないことはないといえるでしょう。
そもそも4両用の汎用特急編成がいない
これはもう死活問題ですよね。これはもともとの特急に関する関心…というか東武鉄道の運用量数の時代の思想の違いが出てきているものだと思います。
もともと一番最初に始まった東武特急、特に日光特急の繁栄期の少し前の車両である5700系にその考え方が顕著に出ています。かつての東武鉄道では必要に応じた増解結をメインとする運用をするのが一般的だったため、半分の車両は増解結が可能な貫通型編成、また別の車両は日光線のフラップシップのような運用をするために当時の湘南顔を採用し、さらに種別を表すヘッドマークの周辺にネコのひげのような紋様が施されていたことから「ネコヒゲ」と呼ばれる形態が存在しました。
このように様々な運用を担当することを前提に製造されているため汎用できるような車両や専用の運用列車として運用されました。前者は一時的には姿を消したけれども現在としてはリバティに当たります。後者は現在のスペーシアやスペーシアXなどに当たりますが物理的な後継車はかつての350型になります。この最終的に行き着く先が634型になる、ということです。
この点を見ると臨時で出すことができる最適な運用を持てる適切な車両がもうなくなっちゃったってことですね。まぁ、乗客側の快適性と企業側の使い勝手としては確かにピカイチなもんなんですが。
終わりに
634型も登場してからはや14年、2017年を最後に雄姿を見るのが難しくなりましたが、最近の臨時でよく見れるようになるとイイですね!
とはいってももう日光線をVVVF車以外で駆け抜ける様子を定期的に見られる車両も634とSL大樹だけ。1720型や100系の特急街道も今じゃ500系やN100系がフラッグシップ。3世代前の車両ももう現代のN100中心ダイヤに乗れて来てないのも事実。はたして、634型は今後どうなっていくんでしょう。

- 2025年8月4日まとめ・考察【そういえば】634型の運用が増えた理由を考えよう
- 2025年8月2日その他【今年もコミケ!】オススメの交通手段、再びっ!+α
- 2025年5月2日その他【意外と沼!?】鉄道のトイレな話
- 2025年4月30日まとめ・考察【まさかの追加情報!?】豊住線の最新情報

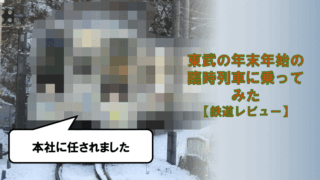



コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。