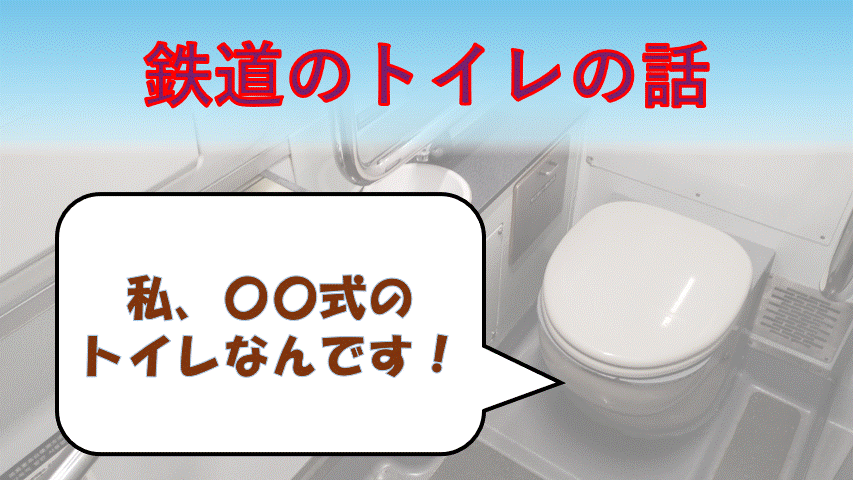
どうも、没話がやけに偏ってきてるなぁとここ最近感じてきているもりやです。
最近は
・新幹線の併結解除された話
・東武鉄道の臨時特急な話
・TX、都営、京王、関鉄のダイヤ改正な話
・収集鉄の切符と交通系ICカードな話
などが没になってちょっとショックだったりします。
さて、そんな中でもなんか専門的な話、ある?って聞かれてふと出てきたんですよ、
トイレ
という言葉が。
じゃあせっかくなら日本の電車の今のトイレの種類とその洗浄方法など書いてみよう!
という事で本日もよろしくお願いします。
トイレの種類
現在使われている鉄道のトイレの種類は大まかに分けて3種類あります。それぞれ
①循環式
②真空式
③清水空圧式
と、呼ばれています。
それぞれに特徴と利点、欠点が存在しますがそれを知るためにはやっぱ前提知識は必要なのでこの中で一番登場が早い循環式の前身にあたる貯留式から話していきましょう。
溜めるトイレ、貯留式
溜めることを前提として設置されたトイレです。
昔から鉄道のトイレは垂れ流しと言い、出したものは全部外、すなわち車外に出していた時代でした。まぁイメージすると車外に通じる穴に出してたわけですね。
だからなんだと。いや、そういう人はいないと思いますがあえて言わせてもらいましょう。だからなんだと。
実はこれ、はっきり言って公害でして。ちょっとイメージしていただきたいのですけれども、あの山陰本線に有名な余部鉄橋ってあるじゃないですか。あそこの下を歩いていると何やら上からなんかの塊が降ってきました。触ってみるとねちょっとした嫌な感触。そう、人のアレ。そう思うと嫌ですよね。それにそれにはたくさんのバクテリアがいて鉄道沿線だけ病気が蔓延しているなんていうパターンもあったらしいです。(因果関係として100%あってるとは言い切れないですが病気にかかるリスクは鉄道沿線、特に幹線沿線がほかの地域よりも高かったらしいです)
ちなみにこの垂れ流しによる様々な問題は「黄害」として話されます。
Q:さて、こんな問題を解決するならどうする?
A:汚水タンクを付ければいいじゃない
ということで作られたのが貯留式のトイレというわけです。さて、この新車なんですが、なんと設置された車両はあの天下の国鉄ではなく、小田急電鉄。これが導入されたのが1950年代の末だったのでこの数年後に小田急は車体傾斜装置の研究を始めてたと考えると当時の小田急はかなりの時代の先駆者ですね。
さて、そんなことは置いといて国鉄でこの貯留式を本格的に採用した車両はかの東海道新幹線0系です。
この時にいろいろと実験をしてタンクの容量が設定されたのですが、なんとこれが500L越え。
合わせて500Lではなくそれぞれ500Lになります。じゃあ大体どれくらいの金額だって話ですけれども現在東海道新幹線は8か所のトイレがありますが、当時は12両だったので6か所と仮定しましょう。1タンクに500Lはいるので総水量は3000L、m3計算すると3m3になります。これを1往復分、さらに1か月全日運用に入るとすると大体2万円程度します。やっぱそれでも安いですね、水道水は。
さて、長かった前提知識はここまでです。それでは現在運用されている3つのトイレを見ていきましょう!
画期的な洗浄方法!?循環式トイレ
さて、東海道新幹線のトイレのうちは良かったんですよ。その時は。
困ったのは山陽新幹線が開通して博多行の列車が運転され始めた時です。この時にトイレの水が足りなくなる!という事件が勃発しました。
そこで「洗う時の水をトイレで流した水分の再利用をしよう」という事で開発されたのが循環式トイレです。
主な搭載車両は西武4000系・東武6050型・211系やE217系などです。
主な清掃方法はボタンを押すと中に溜められている洗浄液がトイレに流れてトイレの洗浄をします。流れた洗浄液やトイレットペーパーなどはゴムである程度隠された穴に落ちてそこで水分と固形物に分離されます。固形物はそのままタンクへ、水分は再利用して再度洗浄液として使用されます。
車両:E217系
提供:こつあず鉄道ちゃんねる
また、この洗浄方法の特徴として流すときに独特な臭いします。この臭いが個人的にはトイレにいるなっていうすごい独特性なので好きっちゃ好きだったのですが。
じゃあこの方法に何か問題がなかったのか、という事ですがこの洗浄方法はこの臭いにあります。
そもそもこの臭い、何なのかというと洗浄液と小さい方です。そう、中に残ってる「水分」を完璧に再利用するために小さい方を出すと洗浄液に混ざって再利用されるという事です。なので、もちろん衛生的に汚いといえば汚いですしなにより小さい方ならともかく、下痢や嘔吐で発生した水分も流れる場合があるためにある程度の日数でこの洗浄液を交換しなければなりませんでした。
それでも、この構造は比較的単純なため、この貯留部分とろ過部分を統合し、ここを使い捨て式にすることで固形物などの抜き取りが難しい路線や車庫にこの抜き取ることのできる設備がない車両などにトイレを設置しやすいという大きな利点があります。(このような方式をカセット式といい、西日本の末期色の車両などが採用しています。)
しかしながらこれだと、先ほど述べた独特な臭いについて対処をしなくてはならず、そこで作られたのが次の2つのトイレとなります。
鉄道トイレの革命児!真空式・清水空圧式トイレ
これらはホントに鉄道のトイレ史において素晴らしいほどの発明となったものたちです。
それぞれ同じ時期に開発され、それぞれ鉄道のトイレの課題を解決するよう作成されました。
段落ではそれぞれ同じように言ってますが、構造や洗浄方法が異なりますのでそれぞれ別に紹介します。
東の革命児、清水空圧式トイレ
清水空圧式は清水、すなわちタンクに入っているきれいな水を高圧で一定時間噴水し、トイレに付着したものを洗い流すという方法です。
水は底にあるフタが開いて中に入る
車両:近鉄80000系(ひのとり)
提供:こつあず鉄道ちゃんねる
もちろん水は再利用されませんので一見すると貯留式に逆戻りしたのではないかと思われがちですが1回あたりに使用されている水の量は200ml。当時の貯留式の水の使用量がおよそ3L、現在利用されている家庭用トイレの旧式(一回水が抜ける方法のやつ)が大と小の平均がおよそ5L、最新式(水がぐるぐる回る方法のやつ)が平均4L、そして鉄道で利用されている男性用トイレの水の量は300mlという事を踏まえると相当節水されていることが分かります。(そもそも鉄道のトイレはいかに節水が大事かというのが要求されてるかがわかりますね)
そして、なんていったってこの方式は汚水タンクまでを重力を利用して落とすために複数個のトイレの洗浄を同時に行うことができるという最大の利点があります。この利点は最近の新幹線や特急など、女性用トイレと男女共用トイレと男性用トイレの3種類が同時に洗浄するといったことも可能です。
そのほかにも汚水タンクへ落とすためのホールが大きいため、ものが詰まりにくい点や清掃時やメンテナンスの容易さなどがあげられます。
しかしながら欠点も存在しており、汚物に対してのにおいが真空式のものと比べて防ぎにくいという点があります。
というのも真空式は水と汚物を一気に吸引して汚物タンクにしまいますが、清水空圧式はそういうわけにはいかないため、臭いが残る場合があります。また、一回水を溜めてから流すわけではないので便器の中にトイレットペーパーなどが張り付いて取れないこと、そして何よりホールが大きい故に何かものを落とすと、(特にスマホ類)入って取れなくなるということが発生してしまいます。
主な搭載車両はE5系新幹線・東武N100系や西武001系・小田急70000形や京成2代目AE形などとなっています。
もちろんここにあるのは関東の車両だけですが、西側で採用されるものももちろんあります。今回こつあず鉄道ちゃんねるさんに提供していただいたこのトイレも近鉄の80000系「ひのとり」もそのうちのひとつです。
しかしながら、相対的には関東圏での採用が多く採用されています。
西の革命児、真空式トイレ
こちらも清水を使って高圧で流す方法ですが、水を抜き取る方法が清水空圧式と異なり、タンクを真空に近い状態にして気圧の変化を利用して水を抜き取るという方法を使用しています。
真空にするための独特な音が特徴
車両:E231系
提供:こつあず鉄道ちゃんねる
この方法はたぶん知ってる方も多いと思います。上の動画を見て一部のお笑い好きの方ならこう思ったに違いないでしょう。
「東海道新幹線のあのネタだ!」と。
どういうことなのかというとあの鉄道ファン芸人で有名な中川家礼二さんの1発ネタ「東海道新幹線のトイレ」のネタです。
「シュー……ゴッ」
の、あのネタです。某番組の鉄道大好き芸人でよくやるネタのうちの一つですね。
さて、そんなことは置いといてこのトイレなのですが、実は本格的に採用されているのは電車ではなく飛行機なのです。
というのももともと飛行機で使用されていた原理を鉄道に流用した、というような感じです。
飛行機のトイレを思い出していただけると幸いなのですが…といっても作者はある程度イメージすることができますが多分皆さんの中でもピンとこないと思うのでどんな構造か解説していきます。
この真空式はトイレの汚水タンクと便器のある部屋の気圧差を利用して一気に水を抜き取る方法です。飛行機では高い高度を飛ぶため、気圧がとても低いです。飛行機内部が0.75気圧~0.8気圧に対して飛行機の巡航高度の気圧は約0.2気圧。そのため、その空気はエントロピー変化(今回使われるエントロピー変化の事象は化学用語でエントロピー増大の法則といいます。イメージとしては紅茶のティーバッグをお湯の中に入れると最初は紅茶の色のついたところと水のところと分かれていますが最終的には均一に混ざりますよね。あれです)をしようとするため水がこの気圧に干渉してタンクに急激に移動します。これが飛行機の真空式です。
この汚水タンクの気圧を下げる方法を人工的に行うことで飛行機の状態に近づけたのが鉄道の真空式です。方式はまず汚水タンクを空圧ポンプで飛行機のトイレの状態と同じ状態にし、ここからは飛行機と同じように気圧の差を使って汚物を吸い込むようになっています。
そしてこの方式の最大のメリットが何といってもトイレを汚水タンクの下に設ける必要がないという点です。
というのもこれは物理的な話なのですが、水を移動する力が前者2つは重力であるのに対してこの方式では気圧差を利用しています。重力よりも気圧差の力の方が強いため、どのような方向にも対応できます。(とはいえ中には固形物もあるため上に持ち上げる、という事は実際にすることは難しいですが。)そのために車両のタンクがついていない車端部にトイレを設置しても物理的に可能なのです。
他にも力が重力よりも吸う力が強いため、吸入口が小さく済みスマホなどを落としても汚水タンクへ流れていかないという利点もあります。
もちろん欠点も存在するわけでしてそのうちの一つに一度トイレを利用すると再度流すまでに30秒から1分間の時間がかかるという点があります。トイレを流すと汚水タンクの中の気圧が一度1気圧まで上がるためにそれを再度低圧にするための時間がかかる、という訳です。
また、このほかにも複数個のトイレを一度に流せないという汚水タンクが大きい故の問題があります。しかしながら、現在では大きな汚水タンクまで移動させる間に小さい汚水タンクを複数個設置することでこの待ち時間を解消してきました。うまく言えば革命児、というよりも今なお革命中ってところですね。
主な搭載車両はN700系新幹線、500系新幹線、東日本では東武634型やE231系、E233系など、多くの車両に搭載されています。しかしながら、東海道・山陽新幹線では当時採用されていた大型のみのものからN700Sの最新式のものまで見られます。そのような点では西側で採用されている、と言えますね。
まとめ
いかがだったでしょうか。こんな感じでトイレにもいくつかの方式があります。もちろんこれ以外にも洗浄方法があります。
今回のこれで鉄道のトイレも沼なんだって知っていただければ幸いです。
今後、トイレがついている電車に乗車する時はぜひトイレに目を向けてみてはいかがでしょうか。
そして今回記事を作成するにあたってこつあず鉄道ちゃんねるさんに動画の提供をしていただきました。この場をお借りして最大限の感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
感想や追加情報、その他指摘などがございましたらコメントしてください!
参考文献
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%97%E8%BB%8A%E4%BE%BF%E6%89%80
wikipedia…列車便所

- 2025年8月4日まとめ・考察【そういえば】634型の運用が増えた理由を考えよう
- 2025年8月2日その他【今年もコミケ!】オススメの交通手段、再びっ!+α
- 2025年5月2日その他【意外と沼!?】鉄道のトイレな話
- 2025年4月30日まとめ・考察【まさかの追加情報!?】豊住線の最新情報

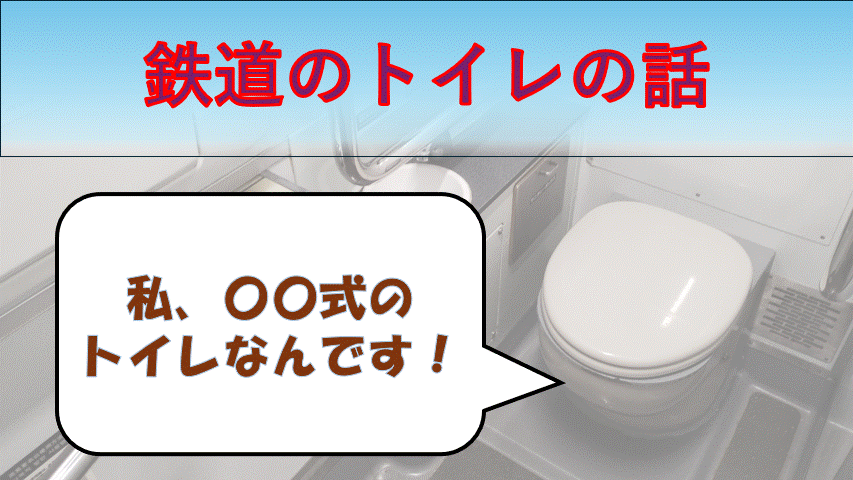



コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。