
どーもどーも。
どうも。そろそろジオラマを作りたい閑古模型です。
いやー…ジオラマに大和か武蔵でも置きたいな……とか考えてたんですけどね。あれ、世界一の戦艦なもんで…1/144に縮めても結構でかいんですよね……。
大和型って全長263.0mの全幅38.9mなんですよね。20m級の鉄道車両に置き換えると、全長がだいたい約13両分、全幅が約2両分…ってとこですかね。全長がE259系の12連より少し長く、全幅が東武8000系の2連より少し短いって考えるとそこそこデカいことが想像できるかと思われます。
と、まぁそんな話は明星か富吉にでもしまっておいて…
今回は、ということを検証していきます。
“プラレール”を“Bトレ”にするってどういうことだってばよ?

月(約45億)
いや“プラレール→Bトレ”ってどういうことやねん!!
……とまぁ、こんな感じに思った方もいるかと思います。
まず、ここでの“Bトレ”を定義しておきましょう。
ここでは、“全長60mm〜70mm” “Nゲージと同スケール”とします。実はBトレって稀に60mmをオーバーする車両がいるんですよね。南海50000系がいい例です。
そして、この定義を当てはめると、“プラレール”を“Bトレにする”ことは“不可能”ということになります。


月(約45億)
えっ…ほな企画倒れやん………
いやいや、そんなことないんですよ。これが。
“プラレール”と言っても、様々な種類があります。
思い出してください。ほら、Nゲージくらいのサイズのプラレール、あるじゃないですか。

月(約45億)
ん……あーあれね。
“プラレールアドバンス”か。

確かに、プラレールアドバンスはNゲージに近いスケールですし、Bトレにするにはちょうどいいかもしれません。

けどね、今回に限っては違うんだな、これが。
今回Bトレにするプラレールは“つなごうプラレール”というものです。いわゆる“食玩”ってやつですね。

聞くところによると、どうやらこのプラレールはNゲージほどのサイズのようなので、Bトレ化するにはちょうど良い気がしてたんですよね。
それで、ある日ふらっとメルカリを眺めていたところ、新品未開封品が安く売られていたので購入しました。
種車を見ていく
そんなわけで、早速開けていきましょう。

まずは本体。
この包装、Bトレと似ていますね。
ちょっとBトレの包装を見てみますか。

(そうでもない……?)
とりあえず、車両本体を取り出してみました。

ボディとシャーシ、車輪とカプラーというパーツ構成は、どこかBトレに通ずるものを感じますね。
一旦ストレートに組んでみます。

組めました。もちろん、動力はないので手転がしかディスプレイ用になります。
付属してきたレールに乗っけてみたのが⤵︎

結構プラレールそのものですね。床とか壁を上手く作ればミニチュアなんかにも使えそうですね。
では、ここで“本物のプラレール”と比べてみましょう。

本物が出てくるとすごくちっさく感じますね……。
これをBトレに……?
では、本題に入りましょう。
この(つながる)プラレールをBトレにできるのか?ということを試してみます。
まずは車体の長さからみていきましょう。今回は、標準的なBトレとして12200系を用意しました。

先頭車(ク80100/ク80600)
まずは先頭車。実車だと、ク80100やク80600にあたる車両ですね。
まずは側面です。


月(約45億)
いやなっっっっっっっが!!!
これ、すっごく長いですよね。
公式ページによると、どうやら先頭車は70mmのようです。Bトレは60mm〜70mmなので、ちょうどいい感じですね。
中間車(モ80200タイプ)
先頭車は長すぎましたが、中間車はどうでしょうか。
というわけで、お次は中間車をみていきます。

これは……短すぎますね………
やはり中間車はプラレール特有のデフォルメが再現されてしまっているようです。(いや一応プラレールなんでこれが正しき姿なんですよ?)
幅・高さ
お次は幅や高さを見ていきます。
つなごうプラレールでは、床下部分も一体成形されているので、この部分を無視します。

うーんこれは……
やはり。こうみるとつなごうプラレールってしっかりプラレールを再現してあるんですね……
プラレール特有の、橋脚による縦方向のデフォルメがかなりされています。
ここで、TOMIX製のNゲージ、近鉄80000系とも比べてみましょう。

(………プラレール、かわいいな……)
とにかく、縦方向を見るにもBトレ転用は無理そうですね……。汎用より屋根の低いひのとりはひのとりじゃない……。
プラレールはプラレールで置いておきます。
ただ、幅は問題ないのでKATO製小型台車の通勤2を履かせればNゲージのレイアウトを走らせることができるでしょう。その場合、先頭動力になりますが……。
内部構造
さて、ここまでは外観的な面を見ていきましたが、ここからは内部構造的な面から見ていきます。
と言うわけで、早速ボディ裏から。

丸い柱が本来のシャーシを支える柱で、その横の横棒は車輪押さえです。
少しずらしてみるとこんな感じ

この部分、Bトレシャーシを載せるとなったらほぼ確実に切り取る必要がありそうです。
ちなみに、このままBトレのHG台車を乗せるとこんな感じになります。

なんというかコレジャナイ感すごいですね…

中間車はやはりフレームより短いので貨物のような見た目になりますね……。
んで、Bトレの台車部分の幅なんですけどね…
これ、ボディ内側の幅とピッタリなんですよ。

これはかなり意外でした。
結論

結論から言うと、“つなごうプラレール”の“Bトレ化”は【無加工では不可能】ですが、【中間車を加工して伸ばすか、KATO製小型台車を取り付けてNゲージの線路を走らせることは可能】ということになります。
まぁ、そもそも規格が違いますからね……。あと、“Bトレ化”をどう解釈するかにもよりますね。
さて、そんなこんなで今回はここら辺で終わります。
YouTubeやTwitterのフォローも是非、よろしくお願いします。
このアイコンが目印です⤵︎
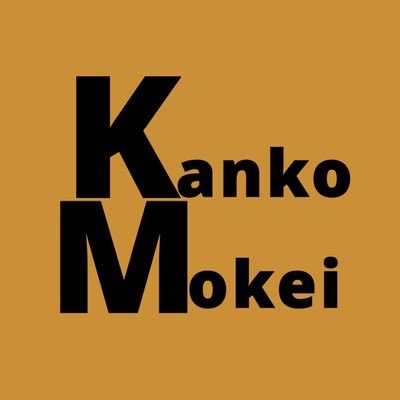
では、また次回!
おまけ:つなごうプラレールの動力化
- 2026年1月14日京阪神【if】近鉄新型一般車を色変え 〜近鉄復刻塗装編〜【勝手に塗装変更シリーズ】
- 2025年12月17日京阪神【名阪伊の青い新車】1A系デビューは1月16日!! プレスの内容を見ていく【近畿日本鉄道】
- 2025年12月14日模型鉄【Bトレ探検 #8】Bトレのシャーシの話【Bトレインショーティー】
- 2025年12月10日もっと【1周年!!】〜Re:Profile〜 改めて自己紹介!!【閑古模型ふりとれ加入1周年記念】





コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。