
唐突ですが、みなさんは「211顔の2両の車両」と言われたら何を思い浮かべるでしょうか?213系、もしくは719系…そんな意見が多いかと思われます。そりゃそうです。だって事実だもん。
では、そんなあなたにこんな問いを投げかけましょう。
「『3ドアの213系』は本当に213系なのか?」
こんばんは。今日も1日お疲れさまでした。
「静岡地区」を長年支えてきた211系電車。国鉄から一部の設計を変え、「別形式」と呼ばれることもあるほどに変更が加えられた、あの電車です。
静岡では、「211系単体の列車はトイレが付いていない!」と嫌われることもありましたね。セントラルライナーが静岡に転属した理由の一つにも、「トイレ設置率を普及させるため」ということがささやかれていました。まぁ211系と共通運用だったので、そういうことなのでしょう…。
そんな静岡211系の中には、「通勤型213系」とも呼ばれた面白い車両がいるのを、ご存じですか?
というわけで、今回は話題沸騰中の「211系6000番代」について、前半では213系電車と比較を、後半では「各私鉄に譲渡された子たち」も一緒に見ていきましょう。
6000番代って何者?

211系6000番代(以下6000番代と呼称)は、1990年に静岡地区向けに投入された、1M1Tという機器構成の211系電車です。
6000番代はまず、1990年に3編成が落成。JR東海の4次車に当たる車両であり、JR東海の5000番代の流れを継承しています。他の5000番代と違い、列番表示器が落成当初から省略されているのが特徴的。また、6000番代オリジナルとして、妻面貫通扉の窓ガラスが大きくなっていることが特徴的です。
当初は御殿場線の輸送力増強として投入されましたが、トイレのない211系は駅間の長い御殿場線での単独運転に適さず、結局東海道線の増結車両として運用されることになります。
ちなみに213系が飯田線に来たのも同じような理由で、中央西線・関西線に2ドア車両というのはやはり似合わなかったらしく、結局トイレを追加で設置して飯田線に転属しています。そのために甲種回送が頻繁に行われていたのはまた別の話。
GG編成は結局成功したようで、翌年1991年には追加で6編成が増備。5次車として分けられており、側面窓がほぼすべて固定されていることが特徴らしく、改めて見てみると本当にほぼすべてが固定窓でした。
なぜ211系なのか?
さて、もう一度問います。
「『3ドアの213系』は本当に213系なのか?」
というわけで、この章では「JR東海の211系は211系じゃない」論とともに、GG編成は本当に211系だったのか、という点について考えていきましょう。
JR東海の211は211なのか

さて、ここ数日SNSで話題になっていた「5000番代は211系なのか」論。様々な意見が飛び交いましたが、僕は「タイプが違う211系」として考えています。
まぁここで言い争っても仕方がないので、東と海の211系を比べてみましょう。
投入線区/置き換え

「■東海道線(東京口)」や「■東北本線(宇都宮線)」などの近郊路線に投入されたJR東車。113・115系初期車を置き換える目的で導入されました。MT比2:3を基本として、初期の車内はボックスシート。近郊型として分類されています。
JR東海にも2編成だけ国鉄時代に211系が配属されましたが、あちらは117系の予備という扱いだったそう。当時名古屋地区では117系の短編成化を行っており、その抜ける編成の補填として2本があてられたようです。
一方のJR東海は、「■中央本線(中央西線)」や「■東海道線(名古屋地区)」などの通勤路線に投入されています。113系のほかに、103系を置き換える目的でも登場。MT比は1:1から2:2が基本。車内はオールロングシートを基本とし、トイレも一部の編成を除き設置されていません。ここが「別形式」と言われる原因なのでしょうか。
見た目


左側の窓(助手席側)と貫通扉、屋根上クーラーの形状が違うのがよくわかると思います。また、スカートについても全然別の形であることがわかります。
JR東海が製造した211系は、ジャンパ管での連結を想定していなかったため、ジャンパ管を省略しています。なお、国鉄時代に製造されたK50編成2本はジャンパ管がついています。ここが2つ目の大きな差ですね。

また、車体側面にスピーカーが付いていること(シンK3/K4/K5とシスGGを除く)や方向幕が一部の車両で3色LED・細いタイプを採用していることがオリジナル車と違うところです。上記の5両編成の211系を見ればわかる…と思いますが、前1両だけ方向幕が細いのがわかりますかね…?


3ドアの213系は213系なのか

というわけで、ここからが本題です。
1M1Tの211系は本当に211系なのか、3ドアの213系は本当に213系なのか。
結論から言うと、211系6000番代は「3ドアの213系」という表現が一番正しい、と個人的には考えています。
実は6000番代、213系5000番代と機器が全く同じなんです。213系の床下に、211系の車体をくっつけた…。それが6000番代。
再末期には213系H9編成の床下機器が故障した際、GG7編成が部品取りを兼ねて廃車されました。ちょうど検査期限も近かったようです。流鉄にGG7編成が譲渡されなかったのはその影響、とも言われています。
213系と6000番代の機器が同じだったからこそできたワザ、なのかも。
しかし、JR東海はドア数で形式を分けている、という噂もあります。結局は「通勤に対応するために3ドアにしたけど、3ドアなら211系でいいじゃん」という発想なのかもしれませんね。
ちなみに余談なんですが、213系の機器はもともと総武快速線向け211系のM車割合を上げるために設計された、と言われています。こちらは国鉄の財政難で結局消えてしまいました。スカ色の211系、少し見てみたかったかも。
そんな1M方式、211系と連結することを前提に作られていたので、JR西・JR東海どちらとも「2M式の211系」と連結することができます。どちらも211系はもういないんですがね…。

まさかの譲渡
どちらも「西武車」の置き換え用として導入されたようです。なお、東海の211系はクモハ211-5001を除き解体されているため、これ以上の投入はない予定です。213系はわかりませんが…。
三岐鉄道
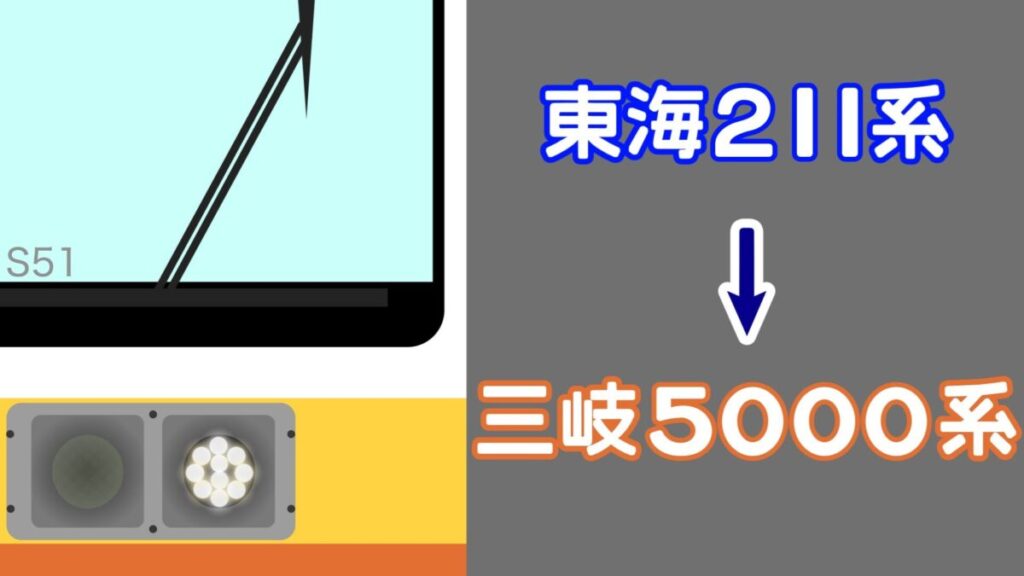
三岐鉄道、211系が入る以前は「801・851系電車(西武701系改造)」・「101系電車(西武401系改造)」・「751系電車(西武新101系電車)」の3グループ4形式が活躍していました。ですが、老朽化が進行していたことなどから新型車へ置き換えることを決定します。
そこで、同時期に廃車されていた「静岡211系」の一部を三岐鉄道が譲受。三岐鉄道「5000系」として運行することに決定しました。「5000系」という名称は、種車が「211系”5000番代”」であったことが由来なんだとか。
現在ではSS2編成を改造した「S51編成」が営業運転に入っています。
S51をはじめとした一部の”5000系になる予定の車両”、すごく面白くてですね…

トイレがない!と不評だったJR東海 中央線の快速電車。結果的にトイレを付けた先頭車と、トイレを付けていない先頭車をトレードすることになります。
その時に「編成間での移動」が起きたため、両先頭車で特徴が異なるのが三岐の一部編成の特徴。片方はJRライトケース、片方は日車ライトケース、方向幕の太さ…。
「JRステンレス電車における車両単位の組み換え」を行った珍しい例でした。
三岐5000の乗車レポートは別記事がありますので是非!
流鉄
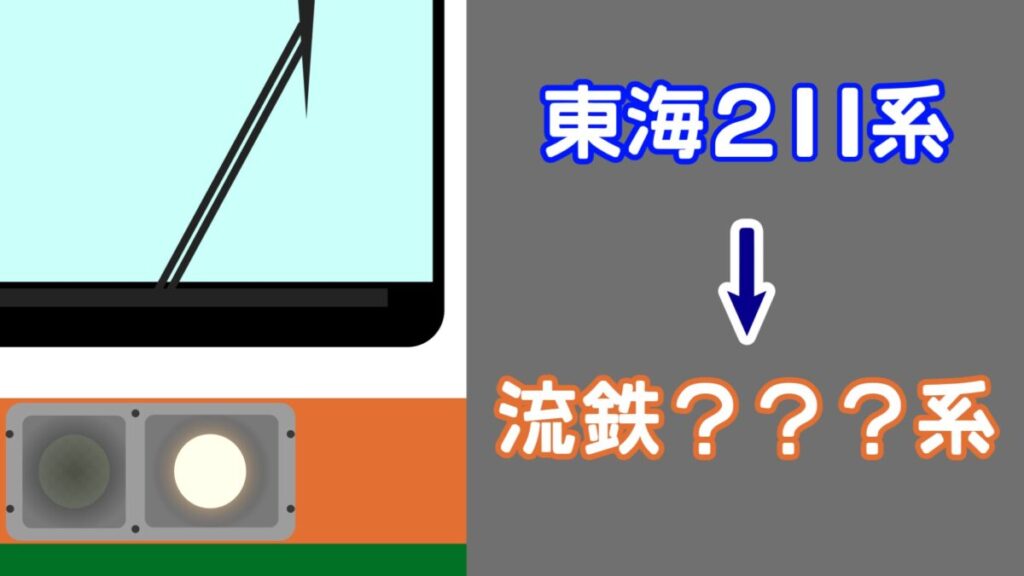
流鉄では、西武の新101系を改造した「5000系電車」が走行しています。
こちら側も老朽が原因で新型車に変えることを決定。流鉄側からJR東海に声をかけ、この譲渡が成立したそうです。
なお、譲渡されたのは「GG5/GG6/GG8/GG9」編成であり、先ほども書いたように「GG7」編成は部品取りとして消えていきました。213系よりも後に登場したのに、最後は213系のために消えていく。やはり、「213系6000番代」として考えるべき車両だったのかもしれません。
改造工事は来年度から。どんな装いになるのかすごく楽しみですね!
ちなみに、馬橋駅で顔を合わせる常磐線には「415系1500番代」という211系そっくりの車両がいました。リバイバル211系顔、として別の角度から注目を浴びていましたね。
まとめ

211系がいよいよ”最後の国鉄型”の1つになろうとしている昨今、211系関連の話題はめまぐるしく動いています。長野車だけでなく、高崎車も、静岡車も。神領車だけがあっけなく解体されてしまいました。
211系なんて新しい、なんて言っていましたがいよいよ今年で40年に入る車がいる状態。今のようなゆるゆるとした状況も、もうすぐ終わるのかもしれません。
一方、各私鉄にとってみればまだまだ新車同然。私鉄に渡った彼らを眺めてみるのも、またいいかもしれません。
そんなこんなで、今回は6000番代、そもそもJR東海211系は本当に211系と呼んでいいのか、ということを持論を交えつつ、車両の性能などから見てみました。結局「211系」と分けられたものは211系なのですから、同じ211系として見てあげるのがいいのかもしれません。同じには見えない、それはわかります。
ついに終わりを迎え始めた211系。最後はどこが残るんでしょうか…。
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
- 晩年眠いので記事の信憑性はないかも(適当)
- 2026年2月8日JR東海213系5000番台、最後のJR東海非VVVF車の歴史を辿る!
- 2026年2月2日東武鉄道鬼は外!👹福は内!🫘秩父鉄道で「豆まき電車」が運行!電車で福を呼び込もう!
- 2026年1月19日JR東日本“横浜線”はなぜ全部”横浜駅”に行かない?~横浜線の歴史を紐解く~
- 2025年12月27日JR東日本中特?通特?青特? 中央線(東京〜高尾)の種別と歴史をざっくり解説!きみも中央線オタクになろう!



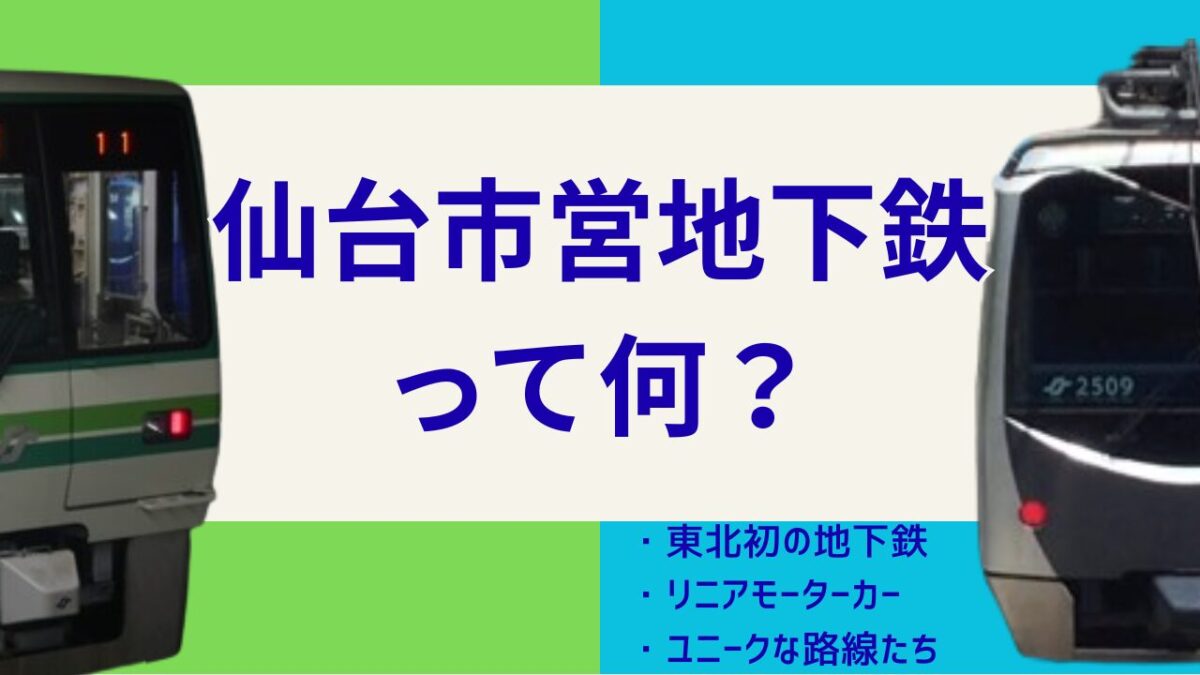


コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。