
こんにちは。こづるしんでんです。皆さんは、「エアポート急行」という列車を知っていますか?
2010年、羽田空港国際線ターミナル(現・第3ターミナル)の開業に合わせて登場し、以降13年間走り続けましたが、2023年11月のダイヤ改正で廃止。名称は「急行」に戻され、エアポート急行は表舞台から姿を消しました。
一見すると「ただの名称変更」。
しかしその裏には、利用者の混乱を招いた中途半端さ、そして多くの迷列車たちの存在がありました。
さらに皮肉なことに、いまなお羽田空港を発着する列車の多くは「急行」で、中身はそのまま生きているのです。
今回は、そんなエアポート急行の生い立ちから廃止、そして復活の可能性までをじっくり見ていきます。
どうして生まれた? エアポート急行の登場

エアポート急行が誕生したのは2010年10月。背景には、羽田空港国際線ターミナル駅の開業がありました。
それまで京急の「急行」は、品川~京急蒲田~羽田空港を結ぶ列車を中心に設定されていました。
しかし羽田の国際化によって、空港アクセス需要が一気に増大。京急としても空港に行く列車はどれか、を分かりやすく示す必要があったのです。
そこで生まれたのが「エアポート急行」。
従来の急行を一斉に改称し、さらに横浜方面や三浦方面へ向かう列車も新設しました。羽田空港アクセスを強調するためのブランド名に近いものでした。
・品川~羽田空港:従来の急行が看板替え
・横浜方面~羽田空港:列車自体を新設
結果、北からも南からも「羽田に行ける急行」がそろったのです。
停車駅

こんな感じです。ちなみにあくまで「エアポート」急行なので品川〜京急蒲田〜逗子・葉山を直通する列車は設定されておらず、全列車が羽田空港発着になっていました。
迷列車誕生 ― 神奈川新町行き

ところが、このエアポート急行、設定の仕方にいろいろ無理がありました。
特に鉄道ファンの間でネタにされたのが「エアポート急行 神奈川新町行き」。
羽田空港を出発した列車が、横浜にも逗子・葉山にも行かず、神奈川新町止まり。
なぜそんな中途半端なところが終点なのかといえば……
答えは簡単、車庫があるから。
神奈川新町は京急新町検車区の最寄駅。車両を入庫させるとき、わざわざ回送するのももったいないから営業化し、さらに普通車だと時間がかかるからエアポート急行の種別にしたのです。
でも「エアポート急行 神奈川新町」という行先表示はやっぱり訳がわかりません。空港アクセスを名乗るのに、着くのは車庫の最寄駅。これはもう、最高の迷列車です……が利用者からしてみればわかりにくいですよね。
他にも羽田空港に向かわず途中駅で終点になる列車が存在していて、出発地も到着地も空港と全く関係ないのに、種別名はエアポート急行。
要するに、誰にとってもわかりづらいという状態に陥っていたのです。
わかりやすいはずが、むしろややこしい

エアポート急行は、本来「利用者にわかりやすく」を目指したはずでした。
しかし現実は逆。
・空港にいかないエアポート急行がある。
・車庫行きの列車が目立つ
・そもそも行き先で案内すればいい
こうした矛盾は利用者を混乱させました。
とくに空港利用者は観光客や外国人が多く、普段から京急に乗っているプロの乗客ではないため、「わかりにくい名称」は致命的。
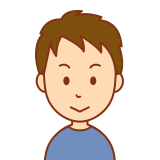
結局、羽田空港行きに乗ればいいんでしょ?
そう考える人が多く、あえて「エアポート」の名称を冠したエアポート急行の存在感は次第に薄れていったのです。
廃止までの流れ

それでも、エアポート急行は13年間走り続けました。ですが、2023年11月、ついに「エアポート急行」は廃止。しかし運行体系はそのままで、名前だけ「急行」に戻されました。そうです。エアポート急行の中身は、今もそのまま生き続けているのです。なぜなのでしょうか?
日中の羽田空港発の列車
±快特:成田スカイアクセス線経由、成田空港行きがメイン
快特:京成押上線経由、青砥or京成高砂まで
特急:北総線経由、印旛日本医大行き
急行:南の方の金沢文庫or逗子・葉山
日中はそれぞれの種別ごとに棲み分けられていて、特に南の方へのアクセスは急行が一手に請け負っています。(品川〜京急蒲田〜横浜〜逗子・葉山を直通する急行はほとんどない)
京急蒲田以南の快特・特急通過駅は、羽田空港をターミナルとして急行にアクセスさせる方が一番良いのでしょう。また、ラッシュ時には羽田空港に来るほとんどの列車は急行になります。
エアポート急行の種別自体は良かったのですが、看板倒れみたいな感じですね……
成功した空港アクセス


ここで少し視点を広げ、他社の「空港系ブランド列車」を見てみましょう。実は「エアポート急行」が迷走した一方で、成功を収めている例も存在します。その代表が 京成電鉄のアクセス特急 と、同じ京急が走らせる エアポート快特 です。
京成「アクセス特急」
2010年、成田スカイアクセス線の開業と同時にデビューしたのが「アクセス特急」。
この列車の役割は非常に明確で、「成田空港へ速く行く一般列車」です。スカイライナーが座席指定・速達型のフラッグシップなら、アクセス特急は運賃のみで利用できるお手軽列車という位置づけでした。
なにより「アクセス」という言葉が利用者に直感的に伝わります。
・成田空港へと直行する
・速い
・空港アクセス専用であることが明確
そのため鉄道に不慣れな人でも案内板を見れば一目で理解でき、ブランドとして定着しました。
京急「エアポート快特」
一方、羽田空港アクセスの花形が「エアポート快特」です。
こちらも役割はシンプル。京成線・都営線方面・品川と羽田を最速で結ぶ看板列車です。快特という京急伝統の種別に「エアポート」を付けることで、「これは空港行きに特化した快特だ」と誰でも理解できる名称になっています。なんなら品川を出たら羽田空港第3ターミナルまで止まりません。
さらに京急の場合は、「快特」「特急」「急行」という棲み分けが明確なので、利用者は「快特=最速、空港直通」と瞬時に判断できる。こうした分かりやすさが、エアポート快特を“成功ブランド”に押し上げました。
エアポート急行との違い
さて、エアポート急行がなぜ失敗したのかを考えると、この2つの成功例との対比で一層際立ちます。
- アクセス特急:必ず空港に行く、役割が明確
- エアポート快特:必ず空港に行く、最速ブランド
- エアポート急行:空港に行かない列車もあった、役割が不明確
要するに「エアポート」と付けるなら、必ず空港アクセスに直結させなければいけないのに、そこを外してしまったのが致命的でした。名称と実態が乖離していたため、せっかくのブランドが利用者の混乱を招く結果になったのです。
復活の可能性はあるのか?

さて、気になるのは「エアポート急行」の復活可能性です。
結論から言えば、可能性は低いと見られます。
京急は2020年代に入ってから「種別の簡素化・統一」を明確に打ち出しており、今さら複雑なブランドを増やす理由がないからです。
また、羽田アクセスはすでに品川方面からの「快特」と「特急」が主役。
急行はあくまで、南からの空港アクセスや地域間輸送を拾う実用列車に割り切られています。
もし復活するのならば、
・空港アクセス用の急行に限定
・羽田空港に直通させる
・運用調整や車庫行きには絶対に付けない
そうすれば「急行」と「エアポート急行」の役割が差別化され、利用者も混乱せずに済むでしょう。
つまり「エアポート快特=速達」「エアポート急行=停車多めだが空港直結」という2枚看板体制が成立するのです。
まあこれでも同じ区間に同じ停車駅の別の種別の列車が走ることになるので、やっぱり推奨はできませんがね……
まとめ
エアポート急行の13年間を振り返ると、浮かび上がるのは名前と実態のギャップです。
エアポート急行は失敗作だったかもしれません。結論として、エアポート急行は“ブランド戦略としては失敗”でした。しかし運行体系そのものは今も生き残り、羽田の日中ダイヤの主役を担っています。つまり「名前は失敗、中身は成功」という不思議な存在だったのです。
けれど鉄道ファンの記憶には、迷列車として鮮烈に残る存在になりました。
いま羽田空港で「急行」を待つとき、そこに13年間走った「エアポート急行」の影を見出すのもいいですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。

-
中央特快相模湖行き()
鉄道madが好きすぎて作り始めました...が、Youtube絶賛放置中です。
iPodが欲しい
水ゼリー大好き
- 2026年1月22日まとめ・考察【仙台駅も】仙石線地下区間駅で接近放送が更新へ【新仙石型?】
- 2026年1月20日まとめ・考察【3度目の塗装変更】キハ110系「おもいで車両」へ、臨時列車も設定
- 2026年1月16日まとめ・考察【ルートも見ていく】仙台市営地下鉄南北線・富谷延伸って何?
- 2026年1月14日まとめ・考察【震災を乗り越えた奇跡の電車】205系3100番台M16編成【仙石線車両図鑑 #16】



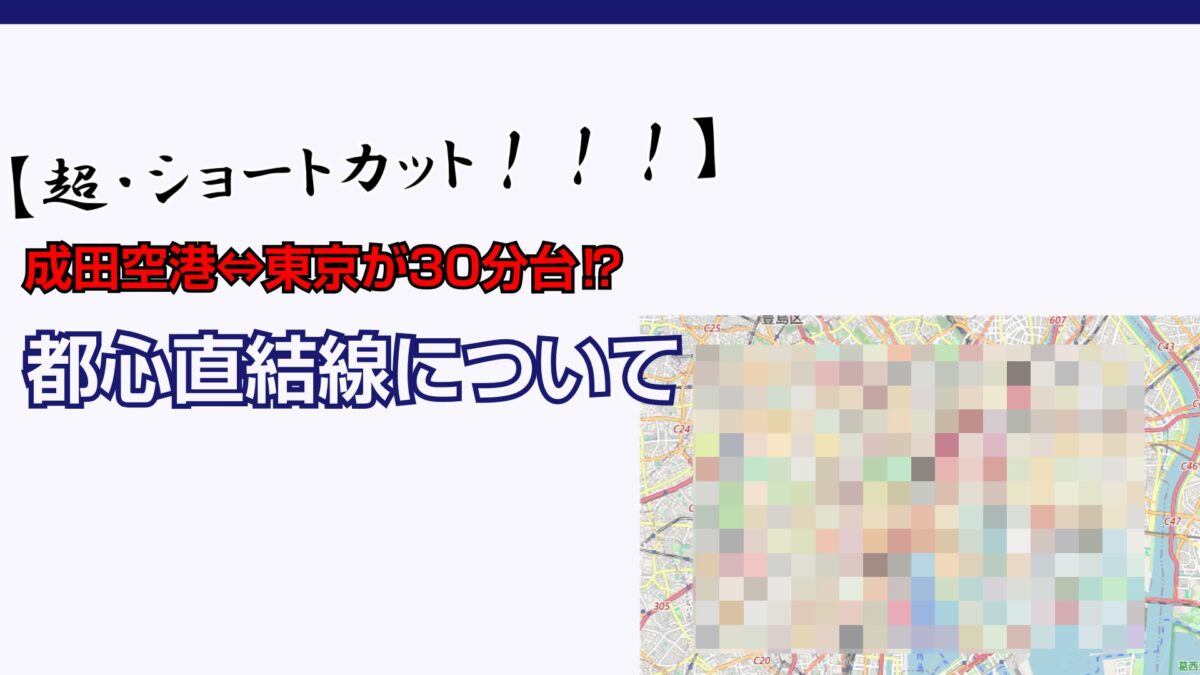

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。