
こんにちは。今回は東武50000系に関して一つ、どうでもいいといえばどうでもいい話について書いていこうと思います。この系列も新車のイメージがいつまでもあったのですがなんと今年でデビュー20周年だそうで……。時の流れって恐ろしいですね。
はじめに:東武50000「系」について
東武50000系は、2005年にデビューした通勤形電車です。東武鉄道の車両として、戦後初の独自設計車両である7800系以来実に46年ぶりとなる日立製作所製の車両であり、同社の標準車両プラットフォームである「A-Train」を採用していることが特徴になっています。それに関連して、東武鉄道の通勤車として9000系以来採用し続けていたステンレスからアルミに車両材質が変更になっており、これはその後60000系・70000系・80000系まで一貫しています(製作が日立製作所なのでおそらく90000系も)。ちなみにカッコ書きで「系」と書いていますが、東武鉄道の車両形式の付け方の特徴として「系」と「型」の使い分けがあります。端的にいえば、「型」というのはJRなどにおける「番台」に相当する細かいグループ分けであり、系列全体を総称する際に「系」が用いられます。50000系の場合
- 東上線地上運用用の50000型
- 本線系統半蔵門線直通用の50050型
- 東上線有楽町線・副都心線系統直通用の50070型
- 東上線座席指定制有料列車「TJライナー」用の50090型
と4つの区分に大別ができます。厳密には主に10030型50番台とかいう形式のせいで「型」がJRの「番台」に相当するという説明は必ずしも正確ではないのですが話がややこしくなるだけなので今回は触れません。そして本記事のタイトルをよく見ていただけると分かるとおり、今回は1番上、一番最初に投入された区分である50000型に関するお話です。
50000「型」導入から現在まで
50000型のトップナンバー、51001Fの落成は2004年のこと。地下鉄半蔵門線直通用の30000系導入が続いていたために久しく新車導入がなかった東上線にとっては10年近くぶりに導入された新車であり、またこれまでの東武独自設計を脱して通勤・近郊電車の標準仕様ガイドライン仕様を考慮し、日立製作所の標準設計「A-Train」を採用。それに伴い東武の通勤車としては初めて車両材質がアルミ製となり、さらに東武の通勤車として今に至るまでもほとんど存在しない前面非貫通構造の先頭車など、これまでの東武の通勤車の「当たり前」をことごとく打ち壊すまさに新時代の車両でした。

今見ても相当特徴的な御尊顔をしておられる。さすがに51002F以降の車両は非常用の貫通扉が付くなど若干の設計変更が施されました。

しかしこの第2編成である51002Fが導入された段階で増備がストップ。代わりに本線系統向けに50050型という新区分が登場します。

東武本線系統は浅草駅が現在に至るまで最大8連までしか入線できず、10連のこの形式は基本的に地下鉄半蔵門線直通専従の車両として落成しました。しかし半蔵門線直通用車両にはこの50000系の前に増備されていた30000系が充当されており、経年的には当然まだまだ若い車両です。なぜこのような形式が起こされたのでしょうか。理由は主に3つあります。
1.東急田園都市線で30000系の分割構造が邪魔になった
半蔵門線を挟んで東武本線系統と直通運転を実施していた東急田園都市線。2000年代の田園都市線の歴史はそれ即ち首都圏屈指の混雑への対策の歴史でした。その一環として当時増備中だった5000系に6ドア車の組み込みを開始したのが2005年。6ドア車は最も混雑する号車に連結することが定石でしたが、田園都市線の場合は5号車と8号車、次いで4号車がそれに該当し、このうち5号車と8号車の2両を6ドア車としていました。
これの何が関係あるのかという話ですが、一般的に鉄道車両というものは先頭車の定員は中間車のそれより少なくなる傾向にあります。東武30000系は6連と4連の分割構造が特徴なのですが、分割構造だと当然中間に先頭車が挟まるわけです。そしてその位置はよりにもよって4号車と5号車だったのでした。

分割構造は最大8連までしか浅草駅に入れない東武本線系統の地上運用でも供するためというのがメインの目的であり、半蔵門線直通そのものには基本的に不要な構造でした。それゆえに早々に置き換えが決まったのです。
ちなみに、東日本大震災以前は田園都市線内から伊勢崎線の太田駅まで直通する臨時列車が年数回運転されており、全く分割構造が邪魔なだけだったかといえばそういうわけではないのですが(伊勢崎線で10連が入線できる北限は館林駅)
2.南栗橋車両管理区の成立
しばしば「周りに何もない」「寝過ごしたら最後」などと散々な取り上げられ方をすることのある日光線の南栗橋駅。実際、そもそも駅の開設自体が1986年とかなり歴史の浅い駅であり、開設と同時に設置された留置線が段々と規模を拡大していったのが南栗橋車両管理区なので、逆に言えばそれを受け入れられるだけの土地があった裏付けでもあるのですからそう言われるのもまぁ当然というべきか。
そしてこの南栗橋車両管理区の成立において最も重要なのが工場機能の移転でした。それまで東武本線系統の車両工場には西新井工場と杉戸工場の二つがあったのですが、いずれも6連以下の車両までしか分割せずの検査などができない手狭な工場になっていました。さらに言うなら先述した30000系が分割構造で落成したのも、この事情が無関係ではありませんでした。
しかし2004年に先述の二つの工場を統合、移転した南栗橋工場が開設され、それをもって南栗橋車両管理区が成立します。この新しい工場は10連の車両を分割したりせずにそのまま検査できるなど、非常に充実した設備を誇る工場となっており、この工場の開設でついに東武本線系統への10連貫通編成の投入が可能になったのです。
なお2009年には南栗橋車両管区に改称。野田線の車両基地であった七光台研修区を傘下に納め現在に至ります
3.そもそもの半蔵門線直通系統の増発、増運用
50050型は2006年3月のダイヤ改正で営業運転を開始しましたが、この改正は東武本線系統においてかなり大規模な白紙改正となっており、そしてこの改正が現在に至るまでのこの系統のダイヤの骨子になっています。
この改正では、これまで日中は毎時3本が区間準急として運転されていた半蔵門線直通列車が急行として毎時6本に大増発。それまで運転されていた浅草発着の準急(通称赤準急)に代わって一躍東武本線系統の一般優等列車の主力に躍り出ます。直通列車の本数が倍以上に増えたわけで、運用の見直しなどで単純に必要車両も倍増えるわけではないとはいえ当然車両を増やす必要はありました。
50000型増備再開、そして……
こうした経緯があり、2編成が製造された段階で増備がストップし、50050型に増備枠が切り替わってしまった50000型。50050型は2005年〜06年のわずか2年で10編成という破竹の速度で増備が進行し、一旦増備が終わった2007年にも地下鉄副都心線開業に備えた50070型及び座席定員制有料列車「TJライナー」用車両として50090型が増備。50000型は完全に忘れ去られたかに見えました……。
そもそも有料列車用にデュアルシートを装備した50090型はともかくなぜ50070型までもが別形式として落成したのか、理由は先頭車の長さにありました。地下鉄副都心線開業を前に、ATOとホームドアを完備した同線における車両規格の策定が各社でなされたのですが、そこで先頭車の全長が130mm延長されることに。50000型は51002Fには非常用前面扉が付いており、地下鉄への直通もできそうなものでしたが、結局こうした事情から副都心線(及び車両が共通の有楽町線)直通用車両は50070型として別形式をおこされたのでした。
そして50050型の更なる増備も行われた2009年、突如として51003F及び04Fが4年ぶりの50000型の増備車として落成。そう、50070型ではなく50000型としての増備です。さらに言うと50000型(実際には51002F)と50050型の違いとして、車体幅が50050型の方が若干(30mm)細くなっているというものがありますが、今回落成した51003F以降の50000型は全てそちらの車体幅に合わせた構造になっています。これは一見すると非常に不可解な動きで、というのも50000型は先述した通り副都心線及び有楽町線には入れず、東上線地上口限定の運用になります。ですが逆に50070型というのは地下鉄直通運用だけではなく、東上線地上口の運用にも入れるいわば上位互換的存在。もちろん地下鉄直通のための機器分のコスト増加はあるでしょうが、それを差し引いても並行して別形式を増備することについてデメリットの方が多いのではないか、という見立ての趣味者が多かった印象。
そんな一見不可解な動きの答え合わせは51009Fまで増備が完了した約10年後、2019年まで待たねばなりませんでした。
2019年、突如として51008Fが東上線から本線系統に転属。その2年後の2021年には51009Fも転属し、代わりに2本だけ残存していた30000系(31606F+31406F、31609F+31409F)が残り13編成の仲間を追って東上線に転属。これをもって東武持ちの半蔵門線直通車は50000系で統一され、30000系は全車が東上線に集結しました。
そう、50000型の増備が50070型の後になって行われた理由、そして50050型と設計が揃えられた理由がこれでした。30000系はチラッと上述した太田駅までの直通列車などで若干数残しておく必要があったもののそれも将来的に置き換える可能性があり、かといって浅草駅に入れず半蔵門線直通以外に使いようがない50050型を余分に製造するのも無駄。そこで全ての車両が10両編成で、しかも30000系も運用されている東上線に同設計の車両を配置すれば将来30000系を置き換える段になっても車両をトレードすれば問題ない。確かに理に適った話ではあります。
なぜ形式統一・改番がなされなかったのか
さてこの記事はここからが本番。
現在南栗橋車両管区には2編成の50000型(51008F、51009F)と18編成の50050型(51051Fー51068F)、計20編成もの50000系が配置。日夜、東武スカイツリーライン(ここで初めてこの名前を使う)の半蔵門線直通急行及び準急専従車両として活躍しています。この2形式は運用上の区別もなく活躍しているのですが、ふとこんな疑問が生じてきます。
・南栗橋に転属した時に50050型に編入しなかったのはなぜ?
・さらに言うならそもそも製造時点で50050型と別形式にする必要はあった?
言うまでもありませんが以下の内容は全て筆者の考察、妄想であり関係各所へのお問い合わせはご迷惑になるのでおやめください。
1.そもそもその必要がないから
身も蓋もない、というかこの記事これで終わっちゃう。
でも実際問題、現業の方々にとって2形式の違いを意識する必要性ってどれだけあるのでしょうか。もちろん東武車かメトロ車か東急車か、メトロ車なら3形式の、東急車なら2形式の違いは意識するでしょうが、その2社に比べれば違いはないに等しい2形式です。そもそも違いを意識する必要がないなら形式を合わせる必要もないのでしょう。
2.数字が足りなくなるから
こっちが本旨だったりする。
50050型は18編成が製造され、編成番号は51068Fまでが使用されています。そして50070型のトップナンバーは51071F。
・・・お分かりいただけただろうか。間に挟める編成番号が残り3つしかないことを。
試しに50000型の南栗橋所属2編成を50050型に編入してみましょう。ここでは製造時期などをガン無視して続番に編入します。51008Fは51069Fに。そして51009Fは……51070F。形式変わっちゃったよ。
今更ですが東武鉄道の(10000系以降の5桁形式の一般車の)編成番号について解説。
- まずほとんどの私鉄同様、東武鉄道もJRのようなきちんとした編成番号が存在せず、1号車の車両番号を便宜的に編成番号として(主に趣味者は)供している
- 万の位の数字は大枠の形式名、東武の「系」に当たる数字が該当
- 千の位の数字は編成内での号車、つまり編成番号としては必ず「1」で固定
- 百の位の数字はその編成の両数、例えば10両編成なら「0」、6両編成なら「6」となる
- 十の位以下の二桁で製造された順番を表す
形式内でのトップナンバーは基本的には下一桁は「1」になるのですが、唯一の例外として試作車としての要素が強かった10000系10080型は唯一在籍した4両の1編成が11480F、となっており下一桁が「0」となる51070Fであっても恐らくは50070型として認識される可能性が高いです。
つまり意図的に改番をしなかった、というよりできなかったのではないかという説です。さらに言うなら実質的なデフレナンバー、すなわち数字が枯渇したために数字を小さくして対処したようなものではないのかというものです。
このデフレナンバー、有名なところだと東急8090系の事例でしょうか。東急の場合、下二桁が製造順を表すという点では東武と同様なのですが、下一桁は奇数のみであったために5編成製造したところでもう数字が枯渇。6編成目は8081F、と数字を10デフレさせて対処したのでした。
東武といえばやはり8000系のいわゆるインフレナンバーが有名でしょうが、実はこのように実質的なデフレナンバーも存在したのです。
そもそも500「50」型の意味は?
結果論ではあるかもしれませんが、50000型の製造は9編成で完了しています。つまり51011F〜51049Fとかなりの数の編成番号に使えた番号が余っているわけです。50050型が例えば50030型、とでも称しておけば編入も全然できたのでは?という疑問が湧いてくるわけです。
その理由について、一つ見えてくるものがあります。10000系以降の各形式で派生形式が誕生した形式は以下の通り
- 20000系→VVVFインバータ制御の採用及び5ドア車を組み込んだ20050型、全車3ドアに戻した20070型
- 70000系→座席定員制有料列車「THライナー」充当用にデュアルシートを搭載した70090型
- 80000系→60000系4号車を改造編入した車両を3号車に組み込む80050型
このうち70000系については下二桁に90番台を使用するのは同じデュアルシート搭載車である50090型であることを踏まえるとデュアルシート搭載車に90を割り当てる規則性が見えてきますが、今回重要なのは残り2形式。20000系と80000系はいずれも派生形式の一番小さい下二桁に50番台が割り当てられています。そして基本形式の製造数は20000型が13編成(21801F〜21813F)、80000型の予定数に至っては7編成(81501F〜81507F?)です。
つまり数字の間隔が空くのは承知の上であえて50番台より小さな数字を派生形式に割り振っていないことが推察できます。流石にその意図まで読み取ることはできませんが、30番台を10000系で使ったきり使っていないのは恐らく偶然ではないのは確かなようです。
まとめ
いかがでしたか?(このワードで締めるのまとめサイトみたいで嫌だけど他に代わる便利なワードがないのも事実)
上述しましたが、恐らく本線系統の現業の方々、特に乗務員の方は全く違いなんて意識してないものと思います。そして利用者も、恐らく趣味者でもなければ違いを見つけることは困難なのではないでしょうか。実際、この2形式はほとんど同じ形式と呼んで差し支えないものであることもこれまで見てきた通りです。
落成時の配属先の違い、たったそれだけのことで別形式とされた2形式。半直系統乗車の際、もし東武車が当たったのなら是非車両番号を気にしてみてください。いわば生まれながらにして生き別れた2つの形式は、一部だけとはいえ今日も肩を並べて久喜〜中央林間という相互直通運転屈指の長距離を走り回っています。

-
仙台支社→東北本部→福島事業本部
動きが目まぐるしい…
- 2026年1月19日乗り鉄【元祖ハイブリッド車】小海線キハE200形を見てみよう
- 2025年12月24日JR東日本【悲願のSuica導入!】しなの鉄道2026年3月ダイヤ改正with北陸新幹線
- 2025年11月21日しなの鉄道【ようこそ】ついに改札機が!しなの鉄道Suica導入に向けた動き
- 2025年10月9日しなの鉄道【C制のエドモンソン券!?】しなの鉄道のハイテク券売機





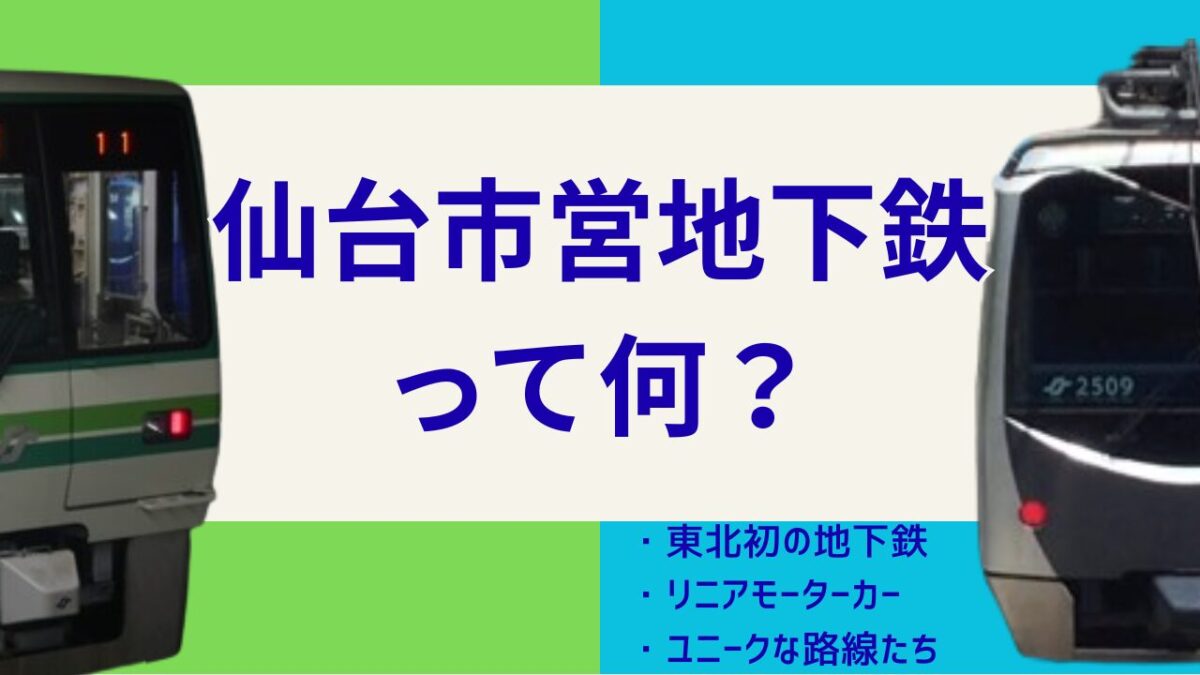

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。