
皆様こんにちは。杉山英澪です。洛嶺電鉄制作記もまもなく回数が二桁に突入。結構長めなシリーズになってきましたね。さて、今回からは3回連続で「洛嶺・奥丹ヒストリー」という名で、洛嶺電鉄・奥丹電鉄やそれらを取り巻く会社の歴史について解説していきます。以下のようなスケジュールで投稿していきます。
- ヒストリー第一回(第 九回):京都電燈の解散まで(〜1942年)
- 第二回(第 十回):洛嶺電鉄の誕生と小浜鉄道廃止まで(1942〜1984年)
- 第三回(第十一回):洛嶺電鉄の現在(1984年〜)
それでは早速行きましょう。
京都電燈の成立
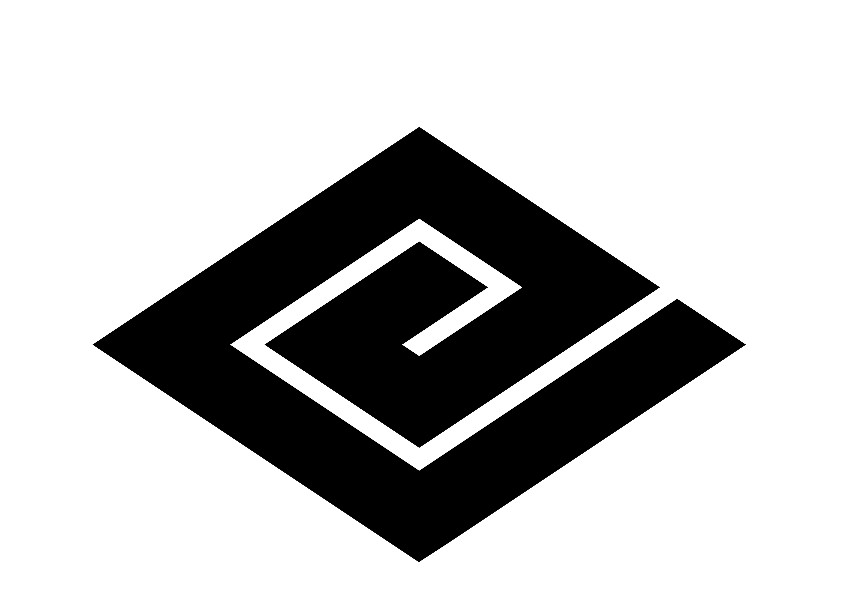
日本初の電力会社は、1883年に設立された東京電燈である(企業活動開始は1886年である)。それに若干の遅れを取り、1887年4月、京都電燈が設立された。日本では4番目の電力会社であった。同社は、1889年に営業を開始した。それと同じ頃、日本初の水力発電所が京都市の蹴上に誕生し、発電を開始した。京都電燈はその蹴上発電所に目をつけ、1892年に同発電所から電力供給を仰ぐこととなった。そうして、京都電燈の供給する豊富な電力は、京都の再興・発展、そして日本初の電気鉄道である京都電気鉄道の誕生に繋がった。以降、1897年に大津支社、1898年に福井支社、1903年に中津支社(大分県)が営業を開始し、事業の拡大を図った。
| 1887年 | 京都電燈会社が誕生。 |
| 1889年 | 本社敷地に発電機を設置。 本格的な営業を開始。 |
| 1892年 | 蹴上発電所の電力を利用開始。 漸次配電線を水力に変換。 |
| 1897年 | 大津支社の営業開始。 |
| 1898年 | 福井支社の営業開始。 |
| 1903年 | 中津支社の営業開始。 |
丹波高速度電気鉄道の誕生
京都電燈の誕生から15年ほどが経った1903年、亀岡から篠山までを天引峠を経由し結ぶ鉄道計画が浮上し、亀岡・篠山の有力者が共同で1905年に丹波鉄道株式会社を設立し、1907年2月に同区間の免許を取得、着工した。同社は京都鉄道(嵯峨野山陰線の前身)と直通し、京都市街地と丹波地方を直接結ぶ列車の運行も計画した。しかしながら、京都鉄道は1907年に国有化され、同線はのちの路線名制定で京都線となった。そんな京都鉄道のかつての重鎮たちは、京都から亀岡を経由し、篠山まで結ぶ路線を計画した。このとき、この重鎮らと丹波鉄道が1908年に合流し、同年8月、丹波鉄道は丹波電気鉄道に改称し、既存の建設中の区間も電化にする旨の計画変更がなされた(1909年1月許可)。それと同時に清水五条〜丹波口〜亀岡の免許も申請し、同年9月に取得した。また、同じ時期に篠山鉄道に合併話を持ちかけ、合意を得た。
1914年5月1日、難工事の末に清水五条〜丹波篠山間が開業した。同時に、篠山鉄道の全線を編入し、京都から篠山口までがが結ばれた。しかし、経営破綻や破産をするほどでは無いものの、利用状況は芳しくなく、利用客の獲得が急がれた。そこで、経営費の削減や粗品の配布などでこの状況を凌ごうとしたが、やはりそれでも限度があった。そこで、篠山方面以外の需要も創造することとなった。そこで、同鉄道が目を付けたのが、1912年に福知山から須知の間を結んでいた福須鉄道(以下、福須)であった。同鉄道も同じく経営危機に陥っていた。そこで、丹波側が福須側に合併話を持ちかけた。これに福須は合意し、1917年4月1日に丹波電気鉄道は福須鉄道を合併した。同時に、社名を丹波高速度電気鉄道(以下、丹波高速)に改めた。その少し前である1915年12月に、丹波電気鉄道は福住から福須の井尻駅までの免許を取得し、翌年に着工した。そして、1917年4月の合併には間に合わなかったが、1917年5月に同区間が開業、京都と福知山が鉄道によって結ばれた。これにより、丹波高速度電気鉄道は一定の経営改善を見た。
以降、丹波高速は北へ、そして西へと延伸を進めていった。まず、1920年2月、丹波篠山から柏原までの免許を申請した。初めは、福知山線との並行を理由に却下され続けていたが、「ルートが違い、かつ福知山線とは異なり地域輸送が主体である」という丹波高速の主張に鉄道省が折れ、1922年に認可された。そして、1924年4月、丹波篠山から柏原までの間が無事開業した。また、1923年4月、柏原から氷上を経由し、佐治(後の青垣)までを結ぶ区間の免許も取得、同区間も1925年7月に開業した。1927年には、亀岡から出雲大神宮への路線を有していた保津人車軌道を合併し、電化させるなど、丹波高速は進化を続けた。
| 1905年2月27日 | 丹波鉄道株式会社が設立。 |
| 1907年2月5日 | 丹波鉄道が亀岡〜篠山間の免許取得。 |
| 1907年8月1日 | 京都鉄道が国有化。 |
| 1908年8月16日 | 丹波鉄道が丹波電気鉄道に改称。 |
| 1909年1月ごろ | 計画変更が許可。 (亀岡〜篠山間の電化) |
| 1909年9月15日 | 清水五条〜亀岡間の免許取得。 |
| 1912年5月27日 | 福須鉄道が開業。当初から電化。 |
| 1914年5月1日 | 清水五条〜丹波篠山間が開業。 同時に篠山鉄道を合併し、同鉄道の全線を編入。 また、同線を電化させた。 |
| 1915年12月11日 | 丹波高速が福住〜井尻間の免許取得。 |
| 1917年4月1日 | 丹波高速が福須を合併。 |
| 1917年5月23日 | 福住〜井尻間が開業。 丹波高速と福須の路線がつながる。 |
| 1920年2月5日 | 申請していた丹波篠山〜柏原の免許が却下。 |
| 1921年4月15日 | (同上) |
| 1921年9月26日 | (同上) |
| 1922年1月26日 | 丹波篠山〜柏原間の免許をようやく取得。 |
| 1923年4月20日 | 柏原〜佐治間の免許を取得。 |
| 1924年4月16日 | 丹波篠山〜柏原間が開業。 |
| 1925年7月1日 | 柏原〜佐治間が開業。 |
| 1927年7月1日 | 保津人車軌道を合併、自社の千歳線とする。 |
| 1927年12月27日 | 千歳線がまで丹波亀山まで開業し、電化。 |
京都電燈の鉄道事業進出
1910年代に入ると、多くの電力会社が鉄道事業に進出するようになった。これは、安定した電気の供給先を確保したり、余剰な電力を使用したりするためのものであり、戦前の電力会社では、東京電燈や宇治川電気もこの施策に取り組んだ。例に漏れず、福井県で電源開発を進めていた京都電燈も鉄道事業に参入することとなり、1914年、福井県下初の電気鉄道として、越前電気鉄道線を開通させた。初めは市荒川駅までだったが漸次延伸し、1918年には、越前の小京都とも呼ばれる大野まで到達した。
京都電燈は、このノウハウを活かして、1918年に現在の嵐山線系統の源流となる嵐山電車軌道を合併した。また、1925年には叡山本線と嵐山本線の支線である北野線、そして永平寺線の前身の永平寺鉄道が相次いで開業した。さらに、1928年には鞍馬線の前身・鞍馬電気鉄道、三国芦原線の前身・三国芦原電鉄、鷹巣線の前身・嶺浜鉄道が、1930年には勝山市街地へ向かう平泉寺線が開業し、現在の洛嶺につながる路線網が一気に形成された。続いて京都電燈が着目したのが、丹波高速であった。当時、急速に路線網を拡大した丹波高速は、収支も増えていったが、それでも経営は苦しかった。一方、京都電燈は但馬地方などの日本海側への進出も目論んでおり、丹波高速はその足掛けになり得る存在であった。つまり、丹波高速と京都電燈利害が一致したのである。京都電燈による丹波高速の併合についての協議は順調に進み、1931年に丹波高速度電気鉄道を合併した。京都電燈は、京都・兵庫・福井の3県に路線を擁する、日本最大級の鉄道事業者となった。
| 1910年3月25日 | 嵐山電車軌道により、京都〜嵐山間が開業。 |
| 1914年2月11日 | 越前電気鉄道線 福井〜市荒川間が開業。 |
| 1914年3月11日 | 市荒川〜勝山(現・勝山口)間が開業。 |
| 1914年4月10日 | 勝山〜大野口間が開業。 |
| 1918年4月2日 | 嵐山電車軌道を合併。 |
| 1918年9月1日 | 大野口〜大野三番(現・洛嶺大野)間が開業。 |
| 1925年9月27日 | 叡山本線として出町柳〜八瀬(現・八瀬比叡山口)間が開業。 |
| 1925年11月3日 | 北野線として、北野〜高雄口(現・宇多野)間が開業。 |
| 1926年3月10日 | 高雄口〜太秦垂箕山間が開業。 |
| 1928年2月24日 | 嶺浜鉄道(現・鷹巣線)が開業。 |
| 1928年12月1日 | 鞍馬電気鉄道(現・鞍馬線)が開業。 |
| 1928年12月30日 | 三国芦原電鉄(現・三国芦原線)が開業。 |
| 1931年4月1日 | 京都電燈が丹波高速を合併。 鉄道の運営を行う部署を「洛嶺電鉄部」とする。 |
但馬電気鉄道の誕生
丹波高速を併合し、但馬地方への進出の基盤が出来た京都電燈は、城崎の温泉旅館らの支援も受け、1931年6月20日、但馬電気鉄道を設立した。同社は、津居山から城崎・豊岡・出石を経て、かつての但東町の中山までの路線を計画した。そして、免許を申請したものの、実際に取得できた区間は、津居山から城崎・豊岡から中山までの区間であった。そこで第一期として、津居山〜城崎間・豊岡〜出石間の建設を開始した。そうして、同区間は1934年6月1日に開業を見た。続いて、出石から中山までの区間の建設に着手し、1936年2月10日に開業を果たした。当初は、ここから先、丹後電気鉄道線(現在の奥丹線の峰山〜間人間に相当する)に接続する峰山までの延伸も目論んだが、資金不足などにより断念した。丹後電気鉄道との接続は、戦後の1971年まで待つこととなる。
| 1921年6月21日 | 丹後電気鉄道線 峰山〜間人間が開業。 |
| 1929年7月21日 | 出石鉄道が開業。 |
| 1931年6月20日 | 但馬電気鉄道設立。 |
| 1932年1月19日 | 津居山〜城崎間・豊岡〜中山間の免許を取得。 |
| 1934年6月1日 | 津居山〜城崎間・豊岡〜出石間が開業。 |
| 1936年2月10日 | 出石〜中山間が開業。 |
| 1944年5月1日 | 出石鉄道の大半の区間が休止となる。 |
小浜鉄道と京都電燈
京都電燈の解体
ここまで大きな成長を遂げてきた京都電燈だったが、流石に戦争の波には屈してしまった。1942年3月2日、京都電燈は配電・発送電事業を関西配電・北陸配電・日本発送電に、鉄道事業を洛嶺電気鉄道に譲渡して事実上の消滅を迎えた。1944年には、会社の清算も結了し、栄華を誇った京都電燈は、半世紀近くにわたる歴史に幕を下ろしたのだった。こうして洛嶺電気鉄道が誕生したが、鞍馬電気鉄道、三国芦原電鉄、永平寺鉄道など、傍系の鉄道会社の併合は、まだ少し先の話となる。
まとめ
ここまで洛嶺の歴史について解説してきましたが、如何でしたか。洛嶺電気鉄道という(きしょい)鉄道会社が如何にして誕生したのかが分かったと思います。次回の記事では、戦後の洛嶺について解説していきます。是非ご期待下さい。
執筆遅延のお知らせ(2025.05.15追記)
杉山英澪です。
さて、この「洛嶺電鉄制作記」シリーズは現在、かなり深刻なネタ不足に陥っています。さらに、杉山本人も多忙であるため、第十回「洛嶺・奥丹ヒストリーⅡ」以降の記事の公開を無期延期とさせていただきます。申し訳ございません。

- 2026年2月6日名古屋鉄道名古屋鉄道 ダイヤ改正2026
- 2025年11月19日東海地方【近況報告】怠慢爆発 架鉄のすぎ〜やま
- 2025年8月18日名古屋鉄道【揺らぐ未来】紆余曲折!名鉄知多新線
- 2025年8月3日その他【名鉄電車】名古屋に次ぐカオスな駅!?〜太田川駅〜






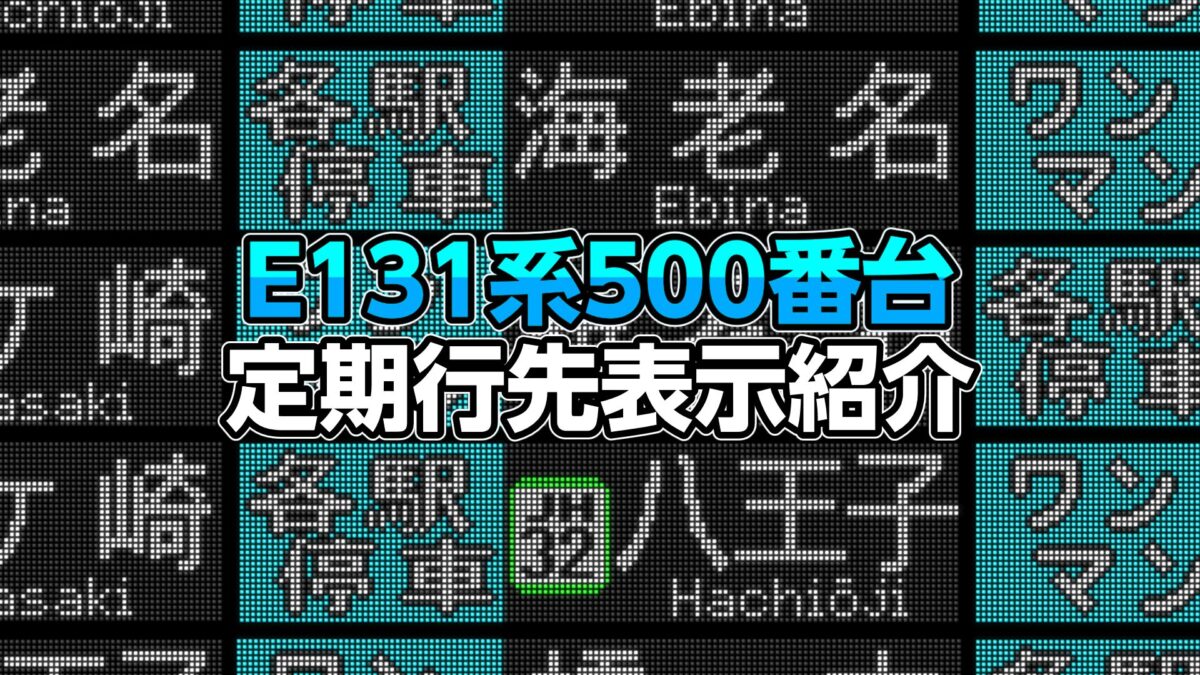


コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。